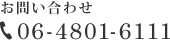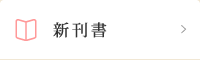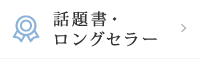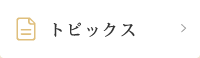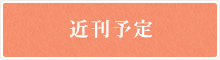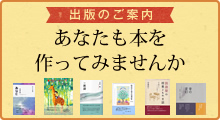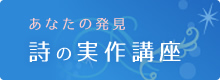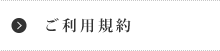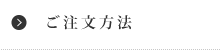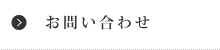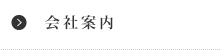![]()
199号 謎(ミステリー)
199号 謎(ミステリー)
- 日が暮れると 吉田享子
- 停留所 田中眞由美
- エコー 桑田 窓
- 『ともしび』の唄 川本多紀夫
- 明け方に逝く人 斗沢テルオ
- 無蓋列車に運ばれて 下前幸一
- CELLO 如月ふう
- 剣道クン 如月ふう
- カトマンズ 升田尚世
- くるまる 白井ひかる
- 銀杏坂 加藤廣行
- 精霊たちへ 森田好子
- 父 来羅ゆら
- 吊り橋 来羅ゆら
- 恨みごと 来羅ゆら
- <PHOTO POEM>母と小舟 長谷部圭子
- <PHOTO POEM>進化論 尾崎まこと
- 野の仏 葉陶紅子
- 小人らと姫 葉陶紅子
- 坂 水崎野里子
- 花 水崎野里子
- 創世記 水崎野里子
- 共生 水崎野里子
- 雨だれ 水崎野里子
- 小バエ 水崎野里子
- ついいも 増田耕三
- スズメ ――巣から落ちた子に 増田耕三
- 一本のコンシーラー 平野鈴子
- アメリカンチェリージャム 平野鈴子
- あの日々があったから 阪南太郎
日が暮れると 吉田享子
昼間の出来事が
二日も三日も前のような気がするのは
なぜだろう
日中がとつぜん掻き消えて
日暮れがぽつんと現われる
いよいよ呆けてしまったか
それとも
あの世とこの世の境目を
知らぬ間に跨いでいて
あっちをうろうろ
こっちをちょろちょろ
徘徊しているのかもしれない
風鈴のような笑い声が
草原のむこうから渡ってくる
懐かしい人たちの声 声 声
なんと爽やかに溶け込んでいるだろう
ああ紫色に暮れ行く空を
カラスがやたらえらそうに
あほーあほーとかえってゆく
おまえはどっちのカラスやねん
停留所 田中眞由美
やまぼうしの咲きはじめた停留所に
バスが停まる
そこには
さよならを言うひとと
またねを言うひとがいる
またねのひとは
行先ばかりが気にかかり
見送るひとを見ていない
さよならのひとは
別れることばかり気にかかり
出かけるひとのすべてを見ようとする
二人の間はとても近いのに
二人の想いはとても遠くて
またねのひとは
前に広がるやまぼうしの道を
いつでも戻ってこられると信じている
さよならのひとは
昨日会ったばかりの人にも
今日はもう会えない事があると知っている
またねのひとはちょっと振り返り
さよならのひとはいつまでも手を振って
やまぼうしの咲きはじめた停留所を
その日初めての客を乗せてバスが出ていく
エコー 桑田 窓
火の鳥は透明な白樺の上で
堪えきれず 夕暮れのうたを唄った
途方にくれた入り口のない泉が
油膜の水面を押し上げたから
自分だけの旅と思い込み
一人立つ 矩形の空は
手の届かない高さで
いろんな道と混ざり合っていた
きみはよく
水しぶきみたく笑っていたね
燃える木々の間に
忘れかけていた弾んだ声が響く
すると泉は
一気に混沌の空へ
昇りはじめる
いまだ 飛び込もう
俺は 自分の弱さを
全て吐き出すために
生き続けるよ
『ともしび』の唄 川本多紀夫
山あいの鄙びた町の停車場に
数人の登山者の
男女たちが汽車から降りて
『ともしび』の唄を
歌いながら
夜霧の中に消えていった
横長のキスリングの
リュックがわずかに
揺れながら
唄ごえとともに
うら若き男女たちの姿が霧の中へ
しだいに薄れていった
町の通りの小さな
古書店から
古本の匂いが甘やかに香り
文学が まだ麗しかったころ
マルクス・エンゲルスに
期待をしたころ
赤軍合唱団の
ロシア民謡の抒情に
憂愁を覚えたころ
みすずかる 信州信濃の
山々が奥深く
神秘的であったころ
青年の 思想がせつなく
懊悩が
美しかったころ
明け方に逝く人 斗沢テルオ
人はどうして明け方に
逝くのだろう
夜が明けるというに
目覚めが近づいているというに
人はどうして
その前に逝くのだろう
Aさんが逝った
明け方に逝った
――眠るように穏やかに発ちました――
医療スタッフが
駆けつけた家族に伝えた
でも口が少し開いている
言い残したことがあったのだ
逝くときは息を引き取るという
吸い込んだ息はそのまま黄泉に
持っていくのか
母も明け方に逝った
闘病中の長く深かった眠りは
永遠の眠りとなって明け方に逝った
俺も明け方に逝くだろう
夜を徹して鳴いていた虫たちは
明け方には鳴り潜め
雄鶏は出番を待っている
潮も引き始めたそんな明け方
もうすぐ東雲が広がるというに
なぜかきっと俺も
明け方に逝くだろう
旅発ちは明け方がよく似合うのだ
無蓋列車に運ばれて 下前幸一
理由もなく
無蓋列車に運ばれて
その場所も認めず
行方も分からぬまま
僕らは思い知るのだ
不確定なもののあわいに
置かれたこと
逃れようのない運命の咎
たわいのない嘘、幻
干からびた路線のカマキリ
ありったけの知恵を絞り
弔いの意味を探っている
なぜ死なねばならなかったのか
それでも死にきれないのかと
燃え残り
燻る希望と
とぐろ巻く思惑
無数の痛みと断念に
名を与えられることはない
死臭漂う世紀の縁を
無蓋列車に運ばれて
目的も分からぬまま
うわべだけの良心に
通じ合えない論争が続いている
容赦ない熱線が群衆を焼く
おいしい話を求めて
亡者たちが一心に票を数えている
地平線が燃えている
横殴りの雨が村を飲み込む
原発は死の灰を備蓄し
干天には無数のミサイル
かいま見えるのは
爆心地の渦
渋谷スクランブルの渦
国境線に流浪の渦
街角には
買い叩かれたレシートの渦
有刺鉄線の峠道
廃プラスチックの
繁栄と蝕みの渦から
決起せよ!
死にそびれた者たちよ
連鎖する貧窮プランクトン
暗い洞窟のウイルスよ
氷河期世代の
瀕死のオットセイ
疾走する
無蓋列車にひしめく
音のない叫び
CELLO 如月ふう
眠っていた
男がわたしを取り出し
ひきよせ
抱きかかえて
目をつむる
わたしは そっと 目をひらいて
酔いはじめる男の顔を 見上げる
男の中にある メロディーが ハーモニーが
古い古い時代からある楽曲が 響きはじめる
太古からの静寂のなかに
わたしの ささやき つぶやき あえぎ さけび ためいき が
こだまする
遠い 遠い 昔からある
あなたと わたしの いとなみ
私は VIOLIN CELLO
あなたが 抱いてくれる時だけ
生きる
剣道クン 如月ふう
昔だったから
男子は剣道か柔道
女子は創作ダンスが、体育の授業だった
しかも
剣道クンは
剣道部だった
竹刀の厳しい音や
野蛮な掛け声は
かすかな憧れだった
修学旅行の夕食前の自由時間
男の子三人から女の子三人に声がかかって散歩した
地震で崩れる前の熊本城
八百屋の店先で「ビタミンC補給」なんて称して
大きな夏柑をひとつ買って 抱えて歩いた
旅館の下駄の鼻緒が、親指と人さし指のすきまで
ちょっと痛かった
帰り道
剣道クンが
「おつきあいしたい」といった
「おんなのことつきあったことないから、おつきあいしてみたい」といった
「すきだから」といってほしかった
(おんなのこならだれでもいいのかしら)とおもった
正直な 素朴な 誠実な
剣道クン
それっきり
若い日は
どちらも
気づかずに
傷つく
傷つける
でも そのちいさな かさぶたは
そっと
おいておきたい
カトマンズ 升田尚世
図書館前の大通りで
祭り行列があるという
ひどい雨降りで
膝まで水に浸かるのに
決行すると市内放送が流れた
八十六になる祖母が
浴衣の胸をはだけて
山車の端に右手をかける
「H市はネパールと同じ高さだからね
ここから落ちたら
カトマンズまで転がってしまうよ」
しきりに止めたが
呟きながら祖母は
山車によじ登ってしまった
せいぜい四、五人乗りなので
大丈夫だろうという気がしたとき
還暦過ぎの男が
「火を貸してくれ」
横から煙草を突きつけた
「持ってない」
そう答えて首を振る
「でしたら あなた
一度『モライタバコ』
と辞書で引いて御覧なさい」
見ると男は
ゼミの担当教官だったから
慌てて『貰い煙草』の文字を並べた
だがそれは
山車から落ちる合図だったのだ
祖母は半分 体を外に投げかけ
同乗の男たちに取り押さえられている
駆け寄ると
「ネパールと同じ高さだからね
カトマンズまで転がってしまうよ」
眼を開(あ)いて 祖母が笑う
くるまる 白井ひかる
カーテンの隙間から
ほんの少しの光の粒
空気は微塵も動かない
カランとどこかで
音がした
鉄とコンクリートの高層階
空と地面の真ん中あたり
ひょろ長い二本足で
立っているに違いない
枕に耳を押し当てる
ゴォーというかすかな遠い地響き
せせらぎなんかではない
風だ
おぼつかない足取り
どこへ行くの?
床を切ってみると
風になびく一面の草の大海原
壁の向こうは碧空
頭を打ちつけると
流れる血
身体からではなく
心からだ
夏の終わり
ダウンケットに
ギュッとくるまる
じんわり汗ばんでくるけど
かまわない
あなたの肌とは違うけれど
銀杏坂 加藤廣行
コンサートの夜は歩いて帰ろう
銀杏坂を上ろう
オーヴァーの襟を立てて
ジャズ・バーに寄らず
大工町でおでん屋にひっかからず
明日の夜も本番だから
ゲネプロのあとで
ソリスト女史が三楽章の入りを
何度も何度も
チャイコのコンチェルト
ピアノの
こちらは五プルトの外だから
北風の対策を立てた
絶海の孤島でしょうとマエストロが言う
そう そこでは聴かずに棒を見るだけ
オケで奏くなら耳は二の次
目をよくする訓練が欠かせない
むこうが見ていない間に盗んだ
夢のような拍の迷いを
本チャンでシフトを変えるスリル
誰と帰ろうか
精霊たちへ 森田好子
断崖絶壁から身を投げた魂よ
美しい珊瑚礁の海に癒され眠るがいい
浜辺の緑葉のアダンの下で命果てたものたちよ
白波とやさしい波音で安らぐがいい
海に散ったものたちよ
道端で行き倒れになったものたちよ
爆弾で血肉砕け散ったものたちよ
岩場の影で果てたものたちよ
黒土となって花咲かせる母となれ
這いつくばって生き延びたものたちは
決して忘れはしない
名もない遺骨にも安らかにと
両の手を合わせましょう
亡骸が見つからなくても
祈りは世界を駆け巡り貴方の元へ
戦(いく)さ(ゆ)は地獄
いついつ迄もミルクユガフうにげーさびら
*ミルクユガフ:弥勒世果報
*うにげーさびら:よろしくお願いします
父 来羅ゆら
父がいた日
幼かった頃
海で溺れた
波打ち際で遊んでいて突然足下が
崩れさったように無くなり恐怖で竦んだ
そのとき
父が懸命に走ってくるのが見えた
もう大丈夫という感じ
父がいるという体験
父がいた
野良犬
父の愛人にまちがわれたことがある
父と娘という関係に馴染めず
たがいに
とまどっていた父と娘
親子というあり方がわからなくて
戸惑いでふざけるから
きつい言葉で遊ぶから
本当に娘さんですか? と尋ねられた
二匹の捨てられた野良犬は
悲しみのかたちが似ている
曲がった指
父についてまわった神童の二文字
父の一生はこの二文字を削りながら
自分の養い親
先妻の子ども
再婚の妻子との
三つの所帯の口を満たした
数日、終戦が遅れたら
人間魚雷に乗って海底に沈んだ命
生きて帰ったことは
若い父に何を残したのか
父が戦争の話をしたことはなかった
戦後八十年という年
とうに逝った人たちの沈黙と
父の沈黙
晩年
久しぶりに会った父は
指がペンを持つ形に変形していた
――よう働いた手ぇやね
――そうやなぁ
かるく笑って
曲がった指を二人で見ていた
吊り橋 来羅ゆら
霧のなか
揺れる吊り橋の真ん中で竦んでいる
揺れは大きくなるばかりで
躰に力が入らない
行くことも戻ることもできない
無力感に覆いつくされ蹲ったとき
遠くから父の声が聞こえた
――立て、おまえなら歩ける
声を頼りに立ち上がり一歩を踏み出した
一歩、また一歩
いつか橋を渡り切っていた
地面に立った安堵と
生きねばならないこれからの日々の重さ
夢の中の霧が深い
なぜあの時
父の声が夢に出てきたのか
永く会うことのなかった父
いつもうつむき加減で目を合わさなかった父
吊り橋で竦むような生きづらさを
ふらつきながらも生きねばならなかった日々に
突然 橋の上に届いた声
おまえなら歩ける と
しばらくして父の死を知った
遠い日々
覚えているのは父の後ろ姿
ひとりで
時には愛人とふたりで去ってゆく
背を丸めうなだれるような歩き方の父を
子どもの私は隠れて見ていた
会えないまま逝ってしまった
父との別れ
薄い縁の父と子の別れは
後ろ姿を見送る
夢で助けてくれた父
ひとりで去っていく父を
子から父へ
最後のあいさつ
後ろ姿を見送る
恨みごと 来羅ゆら
――あれはひどい場所やったわ
父へ 初めての精いっぱいの恨みごと
父が私と弟を置いて出た家
父の養父母の家
――そうや、あれはあの家で育った者にしかわからんわ
あなたは私に向かって
理解者に出あえた子どもの顔をした
父のまなざしの奥で
子どものかなしみは凍ったまま沈んで
生活費を受け取るために寄った父の家で
言ってみたかった恨みごとが零れた日
あの日
私は
投げ捨てた
親を求める気持ち
愛されたいと願う気持ち
みんな投げ捨てた
どうしようもない欠落を父が抱えていて
父の中に存在しない父親を
求めていた気持ちを
投げ捨てた
体の中を冷たい風が吹きぬけたけれど
乾いたため息で
やわらかいものを捨てた後の
気楽な居場所が見つかった気がした
時が過ぎ
父は疾うに冥界の人となり
老いた私の眼は
薄い暗闇が下りて翳(かす)みはじめている
ふしぎだ
あの日
からだを吹き抜けた風が
吹く夜がある
満天の星が煌めく
清(す)みきった夜
あの日の少女が私の中で目覚める
父もいる
私たちは並んで
風に吹かれている
さびしい
なつかしい
冷たい風に吹かれている
<PHOTO POEM>
母と小舟 長谷部圭子
母という木を削って
小さな木の小舟をつくった
沈まないように
漂流しないように
小舟に そっと 知恵をのせた
やがて 大海へと漕ぎ出していくあなた
カモメの姿を借りて くるくると
小舟の横を飛んでみる
意気揚々と帆を進める小舟
カモメは やがて 別れの時を知り
旋回しながら 小さく 鳴いた
うれしさと よろこびに満ちた声で
ほんの少し 切なさがのこる母の声で
<PHOTO POEM>
進化論 尾崎まこと
詩は言葉の自己批評であるように
進化とは自然自身
の自己批評ではないのか
絶望は人の進化をあきらめた
愚かな結論であって
何故に自然は愚直に未来への歩みを止めぬのか?
億兆の偶然をひとつの必然とするのか?
暗闇のなかの光を歩む詩人のように
野の仏 葉陶紅子
母住まずなりにし屋敷 葎生(むぐらふ)の
幼きわれが 夢も朽ちゆく
よーお出で下さりました 折り目高
頭(こうべ)を下げる 小さき母は
3歳の童女のわれに 足乳(たらち)ねの
母はなりぬる われが娘に
葎生の庭掃くわれは 3歳の
童女となって 母に抱かれる
無礼なる物言いで 父責める子を
夜叉のごとくに 叱れる祖母は
草叢で泣き悔やむ子を 探す母
か細き声に 子は重ね泣く
わが母よ乳足(ちた)らひし母よ 陽だまりに
穏やかに笑み 野の仏たり
小人らと姫 葉陶紅子
7人の小人らは 小暗き森に
人知れず棲み なれを見守る
顔手足失くせし姫よ 14の
眸(め)に囲まれる 夢見ざりしや
顔落とし手足失くせば 小人らは
なれをつくりに どこからか来る
トルソーとなりし姫 欠けし傷口
裸線となって 月下に晒す
傷口ゆ 処女のまま姫姫を産(な)し
不死の小人ら 裸線に侍る
姫と姫 裸線と裸線からませて
木漏れ日に濡れ 戯れ遊ぶ
ながいのち欠けてさえ われら小人が
裸線に織り込み 永遠(とわ)に護らん
坂 水崎野里子
坂は上(のぼ)るためにある
坂は下るためにある
上れば下る
下れば上る
そのために坂はある
簡単に上れる坂
息が切れる坂
途中で休む坂
汗が滴る坂
人生は坂だ
歩けるか
歩けないか
そんなこと
神は考えてくれない
足が萎えたら
杖をつこう
車椅子で上ろう
それでも
上れなかったら
あきらめて
ひっくり返って
青空を見ていよう
雲を眺めていよう
神が微笑むまで
花 水崎野里子
花は咲く
生きる
花は
枯れる
萎む
枯れた花
わたしの花
創世記 水崎野里子
始めに光があった
始めに言葉があった
どっちだっけ?
忘れた
人はどうして
終末論を希求するのか?
光を否定し
言葉を投げ捨てる
そして命を
やさしさを?
でも
暗闇から
創世記は始まる
共生 水崎野里子
ヒトと野獣の共生
なんて
無理だ
野獣は
ヒトが彼らの
土地を盗み 住み
境界を越えたと考える
野性を卑下するな
ヒトの
傲慢
悲しい物語
空も飛べないくせに
でもヒトよ せめて
工夫せよ 身を守る道具を
傷つけられ 殺される前に
神は創られた 弱いヒトの形に
今年はなぜか多い 熊の出没
雨だれ 水崎野里子
夜 九時過ぎ
気が付くと
ひとり雨だれを聞いている
すこやかな孤独
軽やかな時間
遠のいた
雑踏の記憶
ひそかな雨の音
だが
道路冠水で
飛沫を立てる車
テレビニュースが
報じていた
昨日
獰猛な自然
やさしい自然
ショパンに雨だれという
ピアノ曲がなかったっけ?
今 雨だれのように
落ちる ピアノの音
それは
私の雨だれのピアノ曲?
勉強し残したこと
やり損ねたこと
たくさんあるようだ
雨だれ
外は暗い
部屋は
明るい
電気
ひとり
安堵の
楽しい
孤独
うきうき
引き続く
雨の音
ショパンが
宙に浮く
生きている
わたし
生きている
音楽
こんにちは
ショパンさん
小バエ 水崎野里子
朝
台所に小さな羽虫が
渦を巻いて
しきりに
飛んでいた
飛び回っていた
夫が電気仕掛けの
ハエ取り器を置いたのに?
用なさず
ハエ叩きで叩いてみようか?
でも小さ過ぎて叩けない
やれ打つな ハエが手を擦る
脚を擦る
そう言ったのは誰だったっけ?
殺せません でも
あるいなハエ叩きでは殺されない
新種の小さなハエが現れた?
進化したんだ きっと
小バエさん あなたと一緒ね
生きているのね
生きて行こうね
にんげんが
虫ケラのように殺されて
しまう
この世界
小さな虫が
にんげんのように殺される
この世界
小バエの いのち
わたしたちの いのち
ついいも 増田耕三
体調がすぐれない妻に代わって
味噌汁を作った
冷蔵庫に、はす芋の茎があったので
それを具のひとつとして
作ることにした
はす芋には
いろんな呼び方があって
「つゆいも」とも言えば
「リュウキュウ」とも言う
葉の上に露をためるから
「つゆいも」と言ったのだろう
そして「リュウキュウ」は
琉球から渡来したからだとのこと
私が生まれ育った土地では
「つゆいも」が、さらに訛って
「ついいも」と言った
子供の頃、裏の畑に行くと
自分の背丈ほどもある「ついいも」が
数本立っていた
雨上がりには
広い葉っぱにたまった水を
ころがして遊んだ
「ついいも」を斜め切りにして
味噌汁を作り、お碗によそう
食事を終えた妻のお椀の底には
だいたい、いつも
「ついいも」が少し残されている
スズメ ――巣から落ちた子に 増田耕三
せっかくこの世に
生まれ落ちてきたのだから
もっと我儘をして
ムリをかければよかったのに
たった二カ月で
旅だってしまった
でも、
おまえは楽しそうだった
頭を撫でられるのが好きだった
小さなむくろを埋める前に
頭を撫でてやった
一本のコンシーラー 平野鈴子
十階病棟より見える北摂の山々の広がり。高槻ニトリ・カインズ
の後方に見え隠れする新幹線。この五日間毎朝上り「のぞみ」
206号の通過するのを見ていた。もう何年乗っていないのだろ
うか、急に乗車の欲望が衝動的にわき上がった。線路脇の野洲の
あの工場、瞬きする間に過ぎ去り残像さえも連れ去ってしまう。
小学校四年生から父から虐待を受け、痣と瘤の始まり。その繋が
りでのことと思っていたが何年経っても消えることがなかった太
田母斑。中学生・高校生になっても顔に堂々として居座り続け、
現在に至っている。組替えになる度に「それどうしたの?」とう
るさいほど聞いてくる友の残酷さにウンザリする。思春期の女学
生にとってやりきれない悲しさ。美しい肌が欲しかった。中二の
時、初めて受診したのは大阪福島にあった古い古い建物の阪大病
院だった。ドライアイスで焼く方法でケロイドの跡が残ることを
知らされ治療を見送った。祖母からは大根おろしをつければいい
と言われ試したが痛いばかりで腹立たしかった。姉妹が喧嘩にな
るとハンディキャップのない一番身近な妹から「アザ、アザ」と
言われ疎んじられ、爆撃砲のように心に刺さった。私には切り返
す言葉がみつからなかった。両親も祖母も他人事で深刻には考え
ていない。この子の為に最大限の力を結集して治してやろうとす
る心は私には伝わったことがなかった。寄り添ってくれる人もな
く一人辛苦を耐えるしかなかった長い長い歳月だった。高校生活
が終了し、やっとお化粧ができる学生生活となり、外資系のМ社
の商品を選ぶことにした。楽しい娘時代も華もなく恋愛に積極的
になれるはずもなく無情に時は過ぎてしまった。メークのテク
ニックをマスターすれば上手くカバーでき、何となく顔を上げれ
ば自信が湧いたが、その時の感情を忘れることができなかった。
三十年ほど前、使っていたコンシーラーが廃番になり、さて困っ
た。京阪神の店を回ったが入手できなかった。そこで私は、アメ
リカ人の日本支社長宛に直訴の手紙を送った。火事になっても地
震になっても、すっぴんで外に出ることができません、と。どう
か会社の倉庫を隈なく捜して下さい。お願いします。etc……。
時を待たず返信が届き、貴女の為にピッタリの色を作ってさしあ
げますとのこと。驚くやら恐縮するやら、飛び立つ思いで野洲の
工場に向かった。商品を捜して下さいという願いが、作っていた
だけるという急展開。困ったあげくの手段に、勇気を出して書い
た手紙が、このような運びとなり、ただ感謝、感謝だった。秘書
の方が来られ、お世話をしていただき、十年分の商品二十本を
作っていただいた。しかも、支社長のお計らいで無料であった。
私からは花キューピットで気持ちを届けた。感謝のバラの花を。
そのとき、アクションを起こさないと何も変わらないことを学ん
だ。その十年後、二度目の商品を冥土の土産ほどの量を作ってい
ただき、現在も使用中である。
思えば近江米が頭を垂れて、稲刈の間際の秋だった。この会社の
色々な方の温かい対応を受け、感謝しても感謝しても足りないほ
どのご恩を受けた。多くの美容部員の方々、二度までも丁寧に
作って下さったE氏。私の名刺ホルダーには往時のままの名刺が
時が止まったように私の傍らで見守ってくれている。色合わせの
際さえ遠慮されて私の顔を直視することをせず、化粧品会社の女
性がターゲットという心の大切さを思い知らされた。見事なまで
ガバナンスの利いた企業であった。E氏は律儀と理性を備えた
ジェントルマンだった。風の便りでオーストラリアに移住された
と聞く。E氏にはいつまでもお達者でと心の中でエールを送り続
けている。
私と太田母斑のつきあいはもう永い。神様から授かった苦しみが
なければ私の人間形成は違っていただろう。五体満足ではないか、
目も見えるし耳も聞こえるではないか。あなたがいたからこの心
が培われたのだ。私はあなたに感謝をしなければならない。私と
の愛の伴走者と七十年を。いつも利他の気持ちに心がけているこ
の八十歳を。
竹を組んだ菱型の光悦垣の穴のむこうはどんな道しるべがあるの
やら。
*太田母斑 顔面の片側にできやすい青色や褐色の斑点
*コンシーラー シミ隠しの化粧品
アメリカンチェリージャム 平野鈴子
漆黒のビンの中
まるでイカ墨か墨汁か
ビンを陽にかざすとワインレッドの夢の中
じゃじゃ馬娘のアメリカンチェリーの気むずかしさ
取っても沸き上がる灰汁とのスパイラル
苦境に立ち手こずる私
エンドレスの見果てぬ灰汁取り
熱を加え続け研ぎ澄ます技がいる
出来上がったジャムは凄みをみせる色となる
(お手並み拝見とからかいせせら笑うトランプの声が聞こえる)
私は皮肉を込めてこのジャムをひそかに
「悪魔のトランプ」と命名した
味は濃厚グラマラス
さざ波のようになったこの腕に達成感と存在感が伝わった
甘いワナはかさが半分になりまるでペテンにあったようなもの
悲哀あり
バリエーションを味わう醍醐味でもある
あの日々があったから 阪南太郎
小学校の教師だったあなたは
私の文章力の無さをいつも心配し
新聞の記事を声を出して読ませた後
「そのことについてどう思う」
と言って感想を強要しましたね
私はその度に
「ぼくはお父さんの生徒やないで
ほんまにうるさいなあ」
と心の中で反発していました
しかし今こうして詩を書いているのは
あの日々があったからです
私が帰省する度にあなたは
「おまえのおじいちゃんは、戦争さえなかったら
もっと長生きできとった」
と言いましたね
一九三二年生まれのあなたは
「もう少し戦争が続いとったら
わしも兵隊に行かんなんかった」
とも言いましたね
あなたが必ず読めと言った
「少年H」と「はだしのゲン」を読むと
あなたの教えがよみがえります
私は夜になれば当たり前のように
電気をつけて詩を書いていますが
これが当たり前ではない時代があったのですね
今、私が書きたいことを書きたいように書けるのは
平和憲法があるからなのですね
私はあなたと同じ教師の道は
歩みませんでしたが
あなたの思いを一人でも多くの人に伝えるため
ペンを持ち続けます
あなたの形見の広辞苑を横に置いて