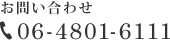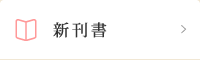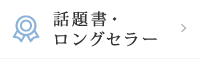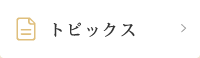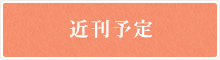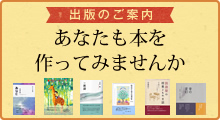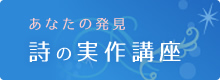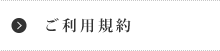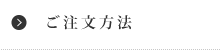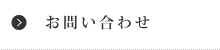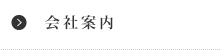![]()
198号 「櫂」の詩人たち
198号 「櫂」の詩人たち
- 人の世 江口 節
- 海の天女 野呂 昶
- カキ氷 後藤光治
- COLORS 中島順子
- 詩は仏様の心 笠原仙一
- 一九九八・「高知豪雨」 増田耕三
- 足跡 加納由将
- うつくしいもの 白井ひかる
- 花の冠 升田尚世
- 影を慕いて 水崎野里子
- 有明の海への旅 ~伊東静雄を偲んで 水崎野里子
- 扇動者たち 下前幸一
- 風の盆 加藤廣行
- 交じり合わない二つ 佐倉圭史
- <PHOTO POEM> バランス 長谷部圭子
- 眼 葉陶紅子
- 磔刑 葉陶紅子
- 蛇を見た日 井上良子
- ある視点 志村京子
- ざらり 志村京子
- チャーパーラ霊樹 志村京子
- 桜 関 中子
- 少年 斗沢テルオ
- 体 門林岩雄
- ふふふ 如月ふう
- 挽歌 如月ふう
- いつもの道で 阪南太郎
- 舟唄 川本多紀夫
- ゴーヤチャンプル 来羅ゆら
- ORIGIN 来羅ゆら
人の世 江口 節
杏ちゃんは学校に行きたくない
女の子二、三人とうまくいかない
三年生
お母さんは思案顔
単身赴任のお父さんは毎週帰ってくれるけれど
そうか 始まったか
私は五年生だったな
昨日までくっついていた仲良しが
ある日突然 聞こえよがしに後で
「ひいき ひいき」 二、三人がすぐ続く
六年生
担任は変わったが事態は変わらず
黙って涙をこぼしていると
前にきて「あら どうしたの」
同じ中学に行きたくない
女は嫌いだ 女子校は受けない
晴れて入学した中学で
生涯の友がふたりもできた
女子だったけれど
社会に出れば、
こそこそ中傷を流すのは男だった
いわく 靡かないやつめ
いわく 先を越しやがって
かく言う本音はおくびにも出さず
十も二十も年上の男のメンツは地雷である*
こわい しつこい
十年二十年 一人消えても次が出る
ああ きたない
こんな世間とおさらばしたい
身近な老若男女が支えてくれるが ――
エジプト考古学の吉村博士は
学内の四面楚歌を突っ走った
冷遇に力尽きた恩師の「負けるな」を胸に
杏ちゃん 今度 ばあばが会いに行くね
*NHKアナウンサー山根基世
「おじさんたちのメンツとプライドは地雷なのよ。」 2023/5
海の天女 野呂 昶
クラゲ
無数の天女が空を泳いでいる
なんという軽やかさ 清らかさ
体のすみずみまでが すきとおり
天衣はないかのようだ
どこからか 天の音楽が聞こえてくる
空はしーんと静まり
ときどき波が
こわいものでも さわるように
手をさしのべる
イソギンチャク
海の底の砂漠に
てんてんと 咲く花たち
いろとりどりの すきとおった花びらが
たえず だれかを まねいている
まねきに誘われて 魚たちがやってくると
すばやく捕らえて 口に運び とかしてしまう
ゆめのように美しく
ゆめのように恐ろしい
苦しみ なやむ者は
つい ふらふらと 迷いこんでみたくなる
シラウオ
手のひらからこぼれた少女の夢が
魚のかたちで泳いでいる
水のように 淡くすきとおり
体の中心には かすかに葉脈のふるえ
月の光が ときめいている
カキ氷 後藤光治
夏祭りの夜
カキ氷屋に入った
母は 嬉しそうに
僕の手を引いて 入った
僕は気後れして
こんなところに入っていいのかと思った
学校に納めなければならない
お金のことを
いつも言い出せずにいたから
シャキシャキした氷を
匙で掬って食べた
母はイチゴのカキ氷を
僕はメロンのカキ氷を
零した氷がテーブルの上で溶けた
母は肘をつき
笑って僕を見ていた
最後に残った
氷水を飲んだ
母は ルビーのような氷水を
僕は サファイアのような氷水を
飲んだ
悲しみに
圧し潰ぶされそうだった
外に出た
浴衣姿で 団扇を持った人々が
祭りの広場へと急いでいた
遠くに 裸電球に照らされた櫓が見えた
藍色の帳の空に
太鼓の音が轟いていた
男に交じって力仕事をしていた母
薄化粧の顔が
とても綺麗に見えた
カキ氷を食べた
あの日
COLORS 中島順子
何色?
きみの見ている風景
きみの目に映る風景
きみのこころの風景
何色?
空は何色?
花は何色?
星は何色?
風は何色?
夢は何色?
うたは何色?
きみは何色?
ぼくは何色?
愛は何色?
世界は何色?
未来は何色?
いのちは何色?
きみの描いていく
この宇宙(そら)の色は
何色?
詩は仏様の心 笠原仙一
詩を書くだけの人ではなく
詩人になりたい
日本の敷島の道に詩の道を付け加えたい
そんな願いを持って
詩の道を追求してきて はや五十有余年
僕ももう七十一歳になった
詩人とはどんな人をいうのだろう
本物の詩とはどんな詩なのだろう
僕はどう生きたら良いのか
詩はどうあるべきか そんなことを
何度も何度も繰り返し考え自問し追究してきた
そして 今 僕がたどり着いた世界は
詩の道は仏様になる道
詩の世界は仏様の心
詩の心は仏の恩・愛の心を感じる心
日本国憲法は仏様の具現の世界
憲法九条は仏様の心 願い
僕は詩人として「仏様のようになりたい」
命あることに感謝し
感謝しながら生きたい
少しでもみんなのために自利利他行で生きたい
命あることの喜びを表現したい
誠実に
働いて働いて
ひととともに 空とともに 光とともに
風や大地とともに
響きあい 思いあい 感じあって
努力精進して新しい世界を創造したい
それはひととして求道者のように
それは追求する芸術家のように
それは妙好人のように
つつましくても自分でつかんだものを
真実を 生きていく確かなものを
愛 ぬくもり 生きるいとおしさを
この手で この体で 自由に 感じて
紡いで
一つ 一つ 表現し 行動していきたい
そう願うようになった
それから 僕は もう 自分の紡ぐ詩に
他人の評価は期待しなくなった
もういい
もういい
この宇宙に生きさせてもらえるだけでいい
この世界にいて
この時にいて幸せを感じるだけでいい
愛する妻よ
愛する子供達よ
愛する地球よ
愛する世界よ
愛する命あるものよ
キラキラと光を受けて輝いているものよ
愛する友だちや優しいひとよ
憲法九条よ
日本国憲法よ
頑張っている 必死に頑張っている
必死に生きている人々よ
みんな友だちだ
共に生きて 喜びを感じあうだけでいい
これから娑婆も自分も何が起きるか分からない
地球は益々怒り 人々の心は迷いに迷い
悪は科学技術と結びついて益々はびこるだろう
でも僕は 与えられた命を
感謝しながら精一杯生きるのだ
それだけでいい
一九九八・「高知豪雨」 増田耕三
「高知豪雨」で被災した
一人の男のことを
書いておかなければならない
幼いころ
私とは、父親ほども年の離れた
従兄のC兄ちゃんが
バイクの後ろに乗せてきた子を
我家の前の用水路のあたりに
ポンと降ろして走り去った
そこには
敵愾心いっぱいの男の子が
顎を引くようにして立っていた
それがKAZUTOSHIだった
どうやら、年下のKAZUTOSHIの
お守役を引き受けさせられたらしい
いまだに、重苦しさしか残されていない
苦難の一日の始まりだった
ちっとも気が合わず、私を手こずらせ
蔑むがごとくの傍若無人さであった
その後も、冠婚葬祭のときなどに
すれ違うことはあったであろうが
言葉を交わすほどの触れ合いもなく
何十年かが過ぎた
KAZUTOSHIは
「高知豪雨」で崩れた
現場の土砂に埋まって死んだ
C兄ちゃんの写真が新聞に載り
KAZUTOSHIは、
現場仕事に転じた矢先の災害だったと
話していた
無念さを滲ませて
その後、KAZUTOSHIの妻は
子を連れて出て行き
C兄ちゃんは
寝たきり同然になったと聞いた
油照りの日に、海辺の斎場で
KAZUTOSHIを送った
足跡 加納由将
ここはどこだ
見覚えのあるものは何もない
とにかく暗い
前が見えないのだ
すすめないのだ
手探りで進んでいく
どこが出口か分からないまま
歩いて行く
やがて
僕は
砂になるのだろう
そして誰かの
足跡になる
うつくしいもの 白井ひかる
花
朝日
夕陽
青空
白い雲
碧い海
ゴールドの輝き
オペラのアリア
美人?
イケメン?
赤ちゃんにお乳を
あげているお母さんの
乳房
潮を噴き上げている
クジラの黒い背中
五月の風に揺れる
透き通った若葉
飛行機の窓から見える
夜の街の煌めき
花火
十五夜の月
満天の星屑
鳥のさえずり
せせらぎの音
富士山
虹
う~ん
それから…
振り返るあなたが
愛してるよって
言う言葉
花の冠 升田尚世
花を摘んだなら
たとえば
百日紅(さるすべり)の房
ふるえる木槿(むくげ) 凌霄花(のうぜんかずら)
太陽の子どもたちを
摘んだのなら
日除け帽を籠にして
美しい歳月を盛ればよい
八月の街路樹
夾竹桃をざわめかせて
風は高く吹き抜ける
鮮やかな緑葉(みどりは)が残酷に揺れる
アスファルトに落ちた影は
夏の踵に踏まれ
沈黙するだけだが
――あの日ワタシ
コトバの礫(つぶて)で
石打ちされてシニマシタ ――
臆病な者たちへ
「もう此処に お前は居ない」
と溢れるほどの散華を
でなければ
籠に盛った一輪ずつを
糸で貫き
花の冠で眠らせよ
影を慕いて 水崎野里子
大阪によく行っていた頃
ある時 住吉大社を訪ねた
伊東静雄の影を慕って
あるいは ひょいと会えないかと
時間の逆転の中で
でも 彼はいなかった
お社(やしろ)の広さだけがそこにあった
彼はヘルダーリンの訳者でもある
ヘルダーリンと共に いつか
広い境内を歩いていると
影が ひょいとあらわれるよ
松の木陰から 清水の中から
きっと
有明の海への旅 ~伊東静雄を偲んで
水崎野里子
昼
日は高く輝き
雲は 青空に棚引き
山々は 頂きに
白い雪を抱いていた
きっと夜には
有明の海は漁師の炊く漁火(いさりび)で
チカチカと 輝き続けるだろう
わたしたちは
ひとつの 影となり
二人で どこまでも
歩いて行った
幻の 有明の海を探して
諫早湾の干拓の彼方
雲仙の麓
島原城からの見晴らし
島原の乱の跡地の下方
有明の海はそこにあった
だが わたしの中で
幻の有明の海がいまだたゆたう
夫に連れて行かれた
夜の諫早の町中
裏町の居酒屋の小粋な中年マダム
まかない飯よと言って
作ってくれた長崎炒麺
今 諫早の町は
ホテルやコンビニ 居酒屋の灯
ネオンサインでキラキラ光る
海のたゆたい
出会った人々は 泳ぐオサカナ
マダム! 諫早の地酒を一杯!
わたしが死す時
雲仙の頂きはいつものように
間白くあれかし
有明の海は
幻の冥土の夜の波で
わたしをやさしく包めかし
幻の漁火は行く手を照らすだろう
有明の月は天心に輝くだろう
扇動者たち 下前幸一
迂回することなく
直截な言葉を投げかけた
冷たい言葉を嘲って
身内の抑揚で囲い込む
論理はインテリの仕草
エリート、大学人、評論家、文化人、
多様性を反駁し
正か負か
半歩先を指し示し
忖度することなく
迷いを見せることもなく
傷口を抉るように
陰謀や言い逃れを徹底的に質すのだ
追い詰めるように
付け入るスキを見せずに
振り向かず
人間らしい素振りで
敵と味方を峻別し
間違ったものたちを踏みつけた
弱さを思い知らせるように
自分を殺すように仕向けるのだ
冷静にそろばん勘定を表明し
反復し扇動するのだ
電子空間に繰り返し拡散し
賛同者たちを焚き付け
強い言葉を
慰み者に向けて
言葉を吐き捨てた
当て付けるように
宛先のない断罪を生贄に押し付ける
投げつけた言葉に魅せられて
匿名のざわめきにそそのかされて
さらに言葉に熱狂した
ふと潮が引いた
ざわめきに見られた
投げ返された言葉に気圧されて
叩きつけた言葉にうろたえた
一瞬の沈黙に血が滲んだ
気持ちの弱さに青ざめた
それは恐怖だともう一人の自分が呟く
言葉は内へと寝返った
思い知らされるままに
平然として居直った
言葉は身内で錯乱していた
気が立っていた
2025年の樹が立っていた
言葉の樹が燃えていた
燃える樹の傍らで動かなかった
風の盆 加藤廣行
月が隠れりや ひとをどり
風が吹く吹く 灯がゆれる
風が吹く吹く 心をゆする
月が出るまで ひとをどり
風がやんでも 心はゆれる
やんでほしいよ なみだ雨
辻を曲がつて 雲の道
月になりたい 沈んでみたい
笠に隠れて いま一度
交じり合わない二つ 佐倉圭史
街路樹と平行に並べられたベンチ
それらの内の一つに腰を掛けていた時に ――
*
道の上、信号機の少し下の辺りの空気の中に
そう、車道の上の「敏速」と歩道の横の「停滞」が
不調和の余りに、決して交じり合わずに
別々の力として存在しているのを確認した
<PHOTO POEM>
バランス 長谷部圭子
追いかけるふりをして
ゆっくりと歩をすすめた
追いつかないように
追いつかれないように
つないだ手の温もりを
覚えていられるように
互いの知恵と感覚で 編み出したキョリ
愛すればこそ
ふたりがみつけた 優しいバランス
眼 葉陶紅子
隣り合う 見えない邑の小人らは
木々の眼となり きみを見ている
娘らを盗み見て 月経の血を
奪いし者の 謂れを歌う
よく響く 人語を話す雌鳥(めんどり)は
ハイビスカスの 乙女なりしと
葉の眼から 精霊ら飛び
青き衣の巨人棲む 邑にたち入る
地を縫って 木の枝々は川となる
大気の色を 見つめすごせば
木屑から生(あ)れし人ゆえ 地に帰る
遍く在って 眼に見えぬだけ
木漏れ日を貌に刺青し 葉擦れ聴き
巨人の傍(はた)で 日がな過ごさん
磔刑 葉陶紅子
衣破(や)れ 衆生の前でま裸の
肌さらされし み咎めゆえか
磔し柱焔やして わが胸を
槍で突きませ 緋き血こぼし
われはここに ま裸のまま彳(た)ちしまま
神なき闇に 肉堕ちるまま
心閉じ 仇怨みてゆく日々の
友みなわれに 背きて去りぬ
天地(あめつち)の闇のはざまに 宙吊りの
裸身晒さん 透きとおるまで
世に出でて妬み嫉まれ 得し幸と
失いし幸 甲斐もあるかな
われ死してそのなき骸ゆ 新しき
人は生い出づ 裸線となりて
蛇を見た日 井上良子
追われて居着いた 来る十月まで
八十年目の夏は近い
家の東 大阪で一番広い池が 大きく咲いている
六月のいま時分は 見事な盛り
光った水は田畑へと西へ下り 北へ進路を変えて
薔薇の咲く東南の庭の角へ 突き当たり
一五二八番地の際を土蔵まで 堀のように沿う
西向きの小さな門脇の 薔薇の根を洗い
光の網を編みながら 一刻も留まること無く
去っていく
小さな門の前には 銀の橋
行き交う時 橋は知らせの音を奏で ろろん
敷かれた石は 玄関口にまで L字に続く
慶応元年と納税書の文字で荒屋が古いと知った
玄関の扉は 壁ごと開くような大きな扉で
扉の中に小さな潜り戸があって
頭を下げ背を丸めて潜り 日常を出入りする
中学校へ行く朝 水路を二匹の蛇が遡って泳いでく
雨があがり 北の空に虹がかかっているのを
廊下の窓から見ていた私に すぐお帰りなさいと
担任が呼びに来た
門の薔薇のアーチに 二匹の蛇が巻きついていた
一息して 祖母が逝った
二階のその部屋の西の窓を 叔母が少し開けた
咲いた薔薇が隙間に見えた
葬儀の日 玄関の大きな扉は内から木槌で叩かれ
開けられた 木槌の音が古い家を 揺り起こす
六月二十一日は夏至だったと気がついたのは最近
ある視点 志村京子
壁の緑色の塗装がひび割れている
剝き出しの鉄骨は赤黒く錆びて瘡蓋のようだ
眼差しでそっと触れる
固定カメラは何時までも動かなかった
ざらり 志村京子
土壁
干からびて反り返った踏板
指先に刺さった棘
チャーパーラ霊樹 志村京子
日差しを避けて木陰に座った
草地の湿り気が身体に伝わる
木漏れ日は美しいだろう
大木にもたれ精霊の声に耳を傾ける
「或る人は、内心に〈物質ならざるもの〉(無色)という想いをいだき、
外面的なもろもろの〈物質的なもの〉を、赤く、赤色の、赤い外観の、
赤い艶のものと見なす。例えば赤く、赤色の、赤い外観の、赤い艶のバ
ンドゥジーヴァカ華のごとくであるとか、あるいは例えば赤く、赤色の、
赤い外観の、赤い艶の、内面が滑らかなぺナレス産の衣のごとくである
と見なして、内心に〈物質ならざるもの〉を想い、外面的な〈物質的な
もの〉をそのように、赤く、赤い外観の、赤い艶のものであると見なし
て、〈それらに打ち克って、われは知り、われは見る〉と、このような
想いをなす。」 『ブッダ最後の旅 大パリニッバーナ経』中村 元 訳
木漏れ日は美しいだろう
頬にあたる風が心地よい
原始仏教はその厭世主義的な性格故にすべてを否定して死に突き進ん
でいく。右に引用した部分は、ヘーゲルの論理学の「本質、現象」に該
当する。アジアの偉大な思想である。
参考文献『ブッダ最後の旅 大パリニッバーナ経』中村 元 訳 岩波文庫
桜 関 中子
咲いて 桜
さくら 次々咲く
家は囲まれ
花のひかり 空は青空
可愛い 蜂はうるさいよ
なぜかな 踊らないわたし
さくらと人の青い静脈
流れをえぐる
何かを分かろうとしない
誰もが分かっている
早すぎる季節と
遅れた迷子
芽生えることもできない失踪
桜 咲いたなら 春 逝けとばかり
ことばに出さずともこころを走る
なんとも身勝手な処世
暗い言い分
おちこち 桜
郷の響きを形象にして
花の さく咲く
映像に声
漢字とかなと…
文字の記憶を重ねる
風が吹く 花吹雪 庭も町もにぎやか
なはずが 洞が この胸に
現われ ゆくえを穿つ
消えるように開いて
雨戸
静かに静と閉めました
今日を待つ昨日を 逃げないようにです
少年 斗沢テルオ
ぼ ぼ ぼくは中学生になったんだ
だ だだ だかだからもう だ だ大丈夫
に にゅ 入学式がちち 近づいてきたので
なな 何度もれ……練習した
は は は はい! はい! は い! はははい!
たたた立ち上がってすすぐに へ 返 事できるように
なな な 何度も練習したした
は は初めてのきょ教室で先生 しし 式の前に
出席を と ととった
そそ そ して体育館に は は 入った
う う後ろを見たら ら
かか 母さん ち ち 小さく手をふ振ってた
一年二組 青木洋 はい! 伊勢了 はい!
加賀昭一 はい! 木田透 はい!
ぼ ぼ ぼくに ちち近づいてき た
き き緊張 でいいっぱいにな な って
前のやや奴 が呼ばれたた
あっ ぼぼくの ばん 番 だ
ぼ ぼぼく は立 ち上がった
へへ へ返 事 へへ 返事 しなくっちゃ
は…は‥‥はは……は…
そそそ そのとき うう後ろ の奴の
な名前 が 呼 ばれた ―― はい!
ぼ ぼ ぼくもへへ返事 しなくっちゃ
は は は は い!
み み 皆んな クスクス わ笑った
せせ 先生は おおかまいなしに次々 に
なな名前を よよ呼んだ
ぼぼぼくは うつつむいて すす座った
うう後ろ ふふ振り向くとかか母さんと目があった
かかか あさん少しうなづいた
ごごめんね かか母さん で でもぼぼぼく
もうへへ平気だ わわ笑われてもへへ平気だ
ちゅちゅ中学生にな ななったんだ
で でも先生 どど どうしてまま待ってて
くれなかったんだろ
ぼぼぼく たた 立ってたのに ――
体 門林岩雄
齢ごとに
体うすくなり
浮いている
今は妻の重みで
辛うじて地上
妻もトシ
やがて二人とも浮くだろう
その頃は
たくさんのひとが浮いている
ひとのことには皆無関心
すれ違っても
あいさつしない
皆上を向いて浮いている
下の子は
どれが親だか分からない
ふふふ 如月ふう
Ⅰ
自分のものではない
そう言いきかせながら
そこにある鼻筋を
ふっと
なぞってみる
生きている限り 覚えておこう この瞬間
決して わたしのものではない
今だけ そこにある
出会えたことを感謝する
億億万劫の彼方
億億万劫の宇宙
そんな中で
ふっと 出会い
ふっと ふれあい
そして
ふっと はなれていく
今は そこにある
今だけの
美しい 鼻筋
Ⅱ
鼻筋をなぞる詩を書いたら
男は これはオレのことだワイと
ひとり ニンマリ 腹の中で ほくそえむ
ふふふ
そんなもんですかねえ
ふふふ
わたしの愛したのは ただ ひとり
そのひとりが
どこの誰だか 知っているのは
わたし ひとり
挽歌 如月ふう
Ⅰ あなたの不在を
あなたの不在を楽しむ
あなたの不在を 味わう
今の今
ひとりぼっちだってことを
さびしいとも
かなしいとも
心もとないとも
わからなくて
あなたの不在を
感じる
味わう
Ⅱ 死体
空まわりしつづけるレコード盤
猫が静かに そこにいる
彼の死体
若すぎもなく
年を取りすぎてもなく
ちょうどの ころあいで
そこにある
曲が終わって 空まわりしつづける レコード盤
眠る 猫
飲みさしの スコッチ
残された 私
Ⅲ 感謝状
おとうちゃま
おはようございます
わたくし あなたの ツマです
おかげさまで
あなたの シゴ
こんな 静かな朝に 目覚めています
ベッドの中で
寒ければ 暖房 暑ければ 冷房のスイッチをいれ
しばらく 布団の中の 自分の体温を 楽しみます
わたしを守ってくれるひとたちは
みんな あっちの世界に行ってしまったけれど
飲み水とパンは
冷蔵庫にあるので 安心です
おとうちゃま
あなたが生きている間は 気がつかなかったけれど
いちおう わたしの命がつきるまで
ひとさまに迷惑をかけずに
毎朝 目覚めておられるのは 幸せです
おはようございます と
おとうちゃまに挨拶できるのは
すくなくとも
おとうちゃまが
一人の女を 守り抜いた というあたりで
神様から 感謝状を 頂ける ということで
おめでとうございます
いつもの道で 阪南太郎
何度も自転車で走った
「桜の通り」と人々が呼ぶこの道を
五月のある日
杖を持って歩くと
道の隅っこに
赤い花
だいだい色の花
ピンク色の花
いろんな花が咲いている
「桜は来年咲くための準備中だけど
私がここに咲いているよ」
という顔をして
ここに咲いてくれた花たち
ありがとう
この花たちを照らしてくれたお日様
ありがとう
この花たちを濡らしてくれた雨雲さん
ありがとう
舟唄 川本多紀夫
小高い丘の
ゆるやかな坂道に沿う
小さな集落の
白壁の家の
レンガ色の屋根越しに
群青色の麗らかな海が見える
それは もうずっと昔の少年のころに
思い浮かべた とつ国の海浜の風景だ
その海原の沖の果てに
霞み立つ浮島の
アドリア海の花嫁ヴェネツィア
水の都ヴェネツィア
それは もうずっと昔の少年のころに
思い憧れた とつ国の都だ
死者を運ぶために
黒く塗られたゴンドラが
河岸に舫いする本島の
遥かな沖合に
死の島 サン・ミケーレが
かすかに煙って見える
文士グスタフ・アシェンバハが訪れて
そして亡くなった
ヴェネツィアの夏
おりしも今は
浮島の あかねさす夕暮れ
ひと節 ふた節
入江の凪の波に 揺られ揺られて
優しき
舟唄こそはあれ
ゴーヤチャンプル 来羅ゆら
ゴーヤの腹を割ったら
真っ赤な種を抱いていた
南の島の鮮やかな花の赤と
血の赤を抱いていた
沖縄の海をひたひたと
あるいはザザーッと
犯し続けるへのへのもへじ
生き物は永遠に沈黙し
かき混ぜ洗う
死者の骨
少女の恐怖に
戦場の匂いが襲いかかる
老女は夜ごと
目覚める細胞の記憶に
唸き声をあげる
忘却を切り裂く赤
忘れられた大地が
裂け目を広げ引き受ける
地下の血だまりは沸騰している
ゴーヤチャンプル
ゴーヤの苦さ
昔ばなしはぶんがくで
混ぜていためて
痛みと苦さは消えるはず
ゴーヤチャンプル
混ぜていためて
みんな忘れて
おいしくいただく
ゴーヤチャンプル
ORIGIN 来羅ゆら
点から始まる
二つの点を
つなげて線にする
直線という名の傷
ORIGIN
受精卵子の回転の静けさ
母と子の起源
いのちは
道しるべのない
まがりみちを
震えながら歩いてゆく
浮かびあがる遺跡
震えるものたちが見上げると
眩しい光が射して
傷と
世界は
濡れてかがやく