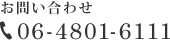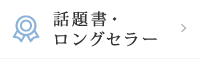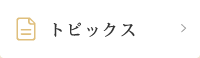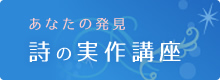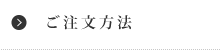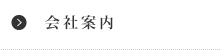![]()
160号 記憶に残る短詩
160号 記憶に残る短詩
- 夜の魔法 武鹿悦子
- 驚いたこと 北岡善寿
- 時代おくれの女 おしだとしこ
- 甍(いらか)の影 青山 麗
- 生のとなり 死のとなり 藤谷恵一郎
- 願望 牛島富美二
- 報道は雨に濡れ 下前幸一
- 洗濯をする 田島廣子
- ゆず風呂 田島廣子
- 蚊に 加納由将
- 逃げる妹 斗沢テルオ
- シシトウ(獅子唐)のうた 吉田定一
- それは 佐古祐二
- 「私は死にそうだ!」――文系学部の叫びに 斉藤明典
- 記憶の中の伝言板 山本なおこ
- ポストまでの近道 蔭山辰子
- 君が泣いている 中島(あたるしま)省吾
- あら大変 ボクちゃんが 水崎野里子
- コロンビーヌ 水崎野里子
- 神々の意匠/女神のモード 葉陶紅子
- 身体としての風景 葉陶紅子
- 泣くということ 関 中子
- 裏 表 晴 静
- 日記 ハラキン
- 母なるもの ハラキン
- 蟬か人か ハラキン
- 自分 神田好能
- 夕影草 本多清子
- なまけもの 根本昌幸
- 〈シリーズ・手〉伝言 原 和子
- 深夜 原 和子
- 小詩篇「花屑」その8 梶谷忠大
- 生き物 日野友子
- 霙降る日の 左子真由美
夜の魔法 武鹿悦子
今夜の月はあんず色
わたしは窓から見ていたよ
とおい森からとびだした
銀にかがやくスプーンが
天秤みたいにかたむいて
月のゼリーを掬うのを
蒼い大きなくちびるが
ゆくての空に浮かぶのを
月のゼリーをのみ込んで
みるみるうすれて消えるのを
わたしはふるえて見ていたよ
熱のある夜(よる) 目がさめて
驚いたこと 北岡善寿
詩を読んで驚いたり感動したりするような
齢でもないのに、詩人自身の言葉ではなくて
詩の中に登場する詩人でない者が発した言葉
に驚いたのは先日のことであった。信州佐久
市在住の詩人酒井力氏の詩集『光と水と緑の
なかに』の中に「夕映え」という一篇があり
そこに「おめえ 完全にゴリラ化しているは
/超やべ」なる一行があった。これは詩人が
電車に乗った時に何人かの女子高生の中から
聞こえて来た嘲笑の言葉である。小説のよう
なフィクションなら、作者の想像でそんな会
話の一端を工夫するかもしれないが、詩は小
説ではないから、このセリフは女子高生の口
から出たものと信用してかからねばならな
い。世間の狭い私は、この言葉に驚いたので
あった。不愉快を伴う驚きと言ったほうがよ
い。「完全にゴリラ化しているは」とはなん
という愚弄か。「超やべ」とくれば、無防備
なこちらはもうギャフンである。酒井氏は俳
諧に詳しい評家のように、女子高生のふざけ
た言葉を「素頓狂な言葉」として受け流して
おられる。私は不愉快な気分を何とか払い除
けようとしてみた。いつの時代でも「今時の
若い者は」年寄りから頭を抑えつけられる。
しかし我慢にも限界があるから、年寄りには
解りにくい比喩を案出して一矢報いることに
なるのが自然の流れだ。私は若者の立場に近
づいたつもりで、「おめえ」という相手を「日
本」に置き換えてみた。そして「完全にゴリ
ラ化しているは」を「完全に植民地化してい
るは」に読み換えたのである。すると「超や
べ」は「極めて危機的だ」になるのである。「や
べ」は「やばい」という隠語を縮めたものだ
が、こう考えるとこのセリフの原意は、「日
本は完全に植民地化している、極めて危機的
だ」であるから、女子高生の現状認識はその
比喩に於て老人顔負けの高さがあることにな
る。「今時の若者は」などと言ってはいられ
まい。何となく願望が開けたような気分にな
るが、これは鈍感な老人の妄想であろうか。
時代おくれの女 おしだとしこ
時代はかわると うそぶきながら
そのときどきの 気まぐれな流れに
うっかり 乗ってしまったら
どこへ 流されるか知れやしない
流行というコトバになじめないものは
アナクロと揶揄されるけれど
時代がどんなに速く流れようとも
時代がどんなにかわろうとも
おのれは おのれでかわりようがない
日本国憲法が公布されたとき
これからは女子も努力しだいで
男子と同様に活躍できる時代になった と
目をかがやかせて語った
先生の言葉に背をおされて
重たい人生の扉を大きく開こうと
あくせくしていたころがあった
OLになって見あげるようなビルの窓から
下界を眺めるなら
世の中のすべてが見えるのだと
錯覚していた時代おくれの女は
身の丈ほどの居場所で
身の丈ほどの暮らしが心地良くなって
身の丈ほどに生きている
子たちの帰る時間にあわせてオヤツを作り
知恵をしぼって貧しい食卓をかざる
時代がどんなにかわろうとも
わたくしは わたくしで
かわりようがないのだと
長い道中の茶店の椅子にかけて
番茶を啜りながら
たそがれ色にそめられている
甍(いらか)の影 青山 麗
いつか見たような
柔らかな陽が落ちる石畳
その上にのびる回廊の甍の影
どこまでも波打つあの日のシルエット
なぜだかしらない
遠い過去にもこの大寺を歩いていたような
あれはいつの時代だったのか
ちょうど今日のような静かな秋の日のこと
今の私が生まれる以前のわたし
しかしそんなことがあり得るのか
いや 確かに五百年も 千年も昔
いまこの瞬間のように歩いていた
まだ私でなかったわたしが
この甍の影の波打ち際をしっかりと
そんな古(いにしえ)の記憶がふと頭をもたげる
ここ奈良の
光よ
風よ
大地よ
生のとなり 死のとなり 藤谷恵一郎
生まれようとして
生まれえなかったものが
寒く暗い宙に
アサガオが秘めやかに開花するように
呼びかけてくる
そのありようしか知らない
無垢なるもののやさしさで
不慮の事故で死んだものが
目覚めのたまゆらに
子どもらしく少し照れながら
座っている
開くはずだった扉の隙間から
零れてくる生命の明るさに向かい
願望 牛島富美二
谷あいの寺を
見下ろしながら暮らす
風が吹き上がるとき
子供たちが下校する
入学したての幼児の声を
上級生が引き取る
すると
時鳥がざわめく
まだ残っていた鶯が
老練な響きをこだまさせる
鶯の宿を借りたに違いない時鳥が
明らかな謝辞を返したと
これは上級生の説明
ああ、こうして季節は繰り返す・・・はずだった
あの日から
鶯が消え
宿をなくした時鳥が消え
鴉が消えて久しく
私の努力を称える
鉄砲百合だけが丈たかく
私の頬を待っているのに
返り咲いた藤の花に絡まれ
風の色は濃く異界のにおいを運んでくる
ああ、こうして季節は断絶する・・・はずだった
けれど
星は休まずに陽を追い続け
陽は休まずに銀河を追い続ける
世の仕組みは人を人として
鳥を鳥としてはぐくむ
あの日は今日へとつながり
今日は明日へとつながる仕組み
ああ、こうして季節は巡る・・・はずなのだ
報道は雨に濡れ 下前幸一
報道は雨に濡れ
しわくちゃになった法案が
冷たい舗道に張り付いて
水たまりは
痩せた月を映しています
いま言葉なく
閉じこもった思いに
ビニール傘をさしかけて
暗い舗道を歩いていると
国会の世間体
ぬるりとかわす答弁や
鬆の入った記者会見
明朝体の条文の
空想の紙芝居
夢見心地の演説や
独りよがりの所信表明
そして国防の恫喝と
襟首をつかんだ強行採決
それらにはじかれた沈黙が
汚れた沼のあぶくのように
私のどこかに浮き上がる
しわくちゃになった法案が
冷たい舗道に張り付いて
報道は雨に濡れ
黄色い落葉の公園に
野ねずみがうずくまる
私はひとり佇んで
葉陰の小さなぬくもりの
鋭い拒絶を見ています
鉛色の空のどこかから
ひそひそと降りてくる
冷たいものに曝されながら
賛否の場所から遠く
はぐれた言葉を探しています
秋深い公園の
濡れた舗道をたどりつつ
傾きながら
木立のあわいを探しています
洗濯をする 田島廣子
わたしは 時間がなくなると、
いらいらしたり 怒ったりする
鏡をみると、こわい顔になる
落ち着くように、わたしは手で洗濯をする
今日 頑張ったなにがしかの汗が
脇や、首から匂ってくる
うれしいときの汗も
怒ったときの汗も
泣かずに、がまんしたときの汗も
服は 全部、知っていた
手で洗うと黒い汁が出てきて綺麗になる
陰日向なく働いたね。生きたね。今日も
と、言っているように聞こえる。
お日様に干せば何か許された気分になる
洗濯物が干してある家をみると
わたしの心は、ほっとしてうれしくなる。
ゆず風呂 田島廣子
今夜は ゆず風呂
猫3匹順番に並んで 目を丸くさせて
わたしと ゆずをみている
だれかーのとき飛びかかったり
わたしを見守っているつもり?
湯舟に浮かぶゆずたち 猫は手でゆずを
沈めたり、浮かべたりしている
ゆずは黄色の裸で泳ぎだして、ぷかぷかと
お尻や乳房と触れ合ってぷあんふあん
わたしの乳房はつきたてのおもちのよう
乳首がふたつ、ぐみの実のように甘ずっぱく
かわいくて 口にふくみたくなる
ゆずの匂いが、さびしいわたしを
華やかに 色っぽくさせる
まだ、女がのこっていて、手踊りすれば、
鏡のなかの裸体が、愛したひとを
もう、会えなくなったひとを、恋しがる。
蚊に 加納由将
耳元を
蚊が過ぎていく
蚊になりたい
ふっと思った
死も一瞬で訪れる
何の苦しみもなく
その時
あなたの
血をいっぱいにいけたなら
懐かしい声が
聞こえた気がした
あなたの
視線のぬくもりに
包まれ
死んでいく
誘惑
逃げる妹 斗沢テルオ
先ず長兄が十五で飛び出した
次いで俺も十五で飛び出した
長女も十五の春に飛び出した
三男は十八の春に飛び出した
飛び出していく兄姉(おれたち)を末妹は
襖の陰から羨望の眼で見送っていた
自分の番が来ると信じていたが
老いていく母がいつも傍にいて
巣立ちの季節が近づくにつれ
うとましさの感情を制御できずにいた
練習もした
その家出騒動に兄姉は集まった
すすり泣く母を前に
末妹の真意計れずにいた
聞こえたか二日後に戻ってきた
目と鼻の先のお堂に潜んでいただけだった
詰る兄姉の声を台所で黙って聞いていた
母は何も言わず食事の支度に台所に立って
末妹と並んだ
母が小さくなったか末妹が大きくなったか
二人の背中が哀しく見えた
十八になっても末妹は
老いゆく母の呪縛から逃げ出すことが
できなかった
幾度となく試みたが兄姉に探し出され
借間の玄関開けようとする母と対峙
内と外でノブ握り合い 二人で泣いていた
実家の小さな家は
二人の葛藤だけが充満した
末というだけで
家に取り残され押し付けられ
やがて待っていたものは介護
しきりに結婚したいと駄々もこねた
結婚すれば逃げることができる
しかしそれも叶わなかった
突然攻撃に走った
兄姉に罵詈雑言の手紙を毎日送り続けた
そして強行突破を図り
逃げて――逃げて逃げて
逃げている最中に母が死んだ
葬儀直前探し当て参列を促したが
半狂乱に兄姉を詰った
今さら何よ!
兄妹って何よ!
家族って何よ!
一人を欠いて母を見送りながら兄姉は一様に
生まれ出た順番をどこかで確認していた
するとどうしても末妹は最後だった
ひと月も経ったか墓前に真紅のバラ
俺は墓に続く林を探した
小さなお堂にあのときと同じように潜んでいた
こんなときのためにと保管しておいた
小指程度の母の骨
末妹は遺骨を握りしめながら
私は兄姉(あなたたち)から逃げているのよ
これからも逃げ続けるから――
末妹よ お前だけが苦しんだのではない
それぞれが生まれた順番で苦しんできたのだ
戻れ! 兄姉の元に戻って来い!
言葉掛けも空しく憎悪の眼差しで
林の中に消えていった
末妹は今も――逃げ続けている
シシトウ(獅子唐)のうた 吉田定一
――四(し)×四(し) 十(とう)だ なんて!
四(し)×四(し) 十六(じゅうろく) ではないの? シシトウさん
――自分の 簡単な計算もできないのにねぇ
――女将(おかみ)! いつまでも屁理屈を叩いていろっ!
俎板の上で シシトウさん 泣いたり笑ったり
顔を赤くして 莩を巻いて酔っぱらっている
(――人生は 泣き笑い、泣き笑いの 人生だ…)
――あら、舌がもえる、しくしく泣けてくる
助けてください、ねえ、シシトウさん お願い
――口は禍のもと、だめです!
シシトウが はっはっと 笑う
――しくしく 泣き泣かされて 四(し)×九(く) 三十六(さんじゅうろく)
はっはっと 笑い笑われて 八(はっ)×八(ぱ) 六十四(ろくじゅうし)
――泣いて笑って 合わせて(三十六+六十四)
百の 泣き笑いの人生 百点満点!
すっかり シシトウさん
酔いから醒めて
もとの青く澄んだ 真顔に納まっている
――ほら、女将さん!
こんな生きた 計算もできないの?
――ん~!?
それは 佐古祐二
妙なもの
心悲(うらがな)しいもの
無口になるもの
内緒
馬鹿げたもの
悩みのたね
きらびやかなもの
つつましいもの
涙ぐむもの
陽気なもの
よいのかわるいのか
イチかバチかやってみるもの
ゆらぎ
胸苦しいもの
放埓なもの
手に負えないもの
落ちるもの
身悶えするもの
狂おしいもの
だが
これだけは
はっきりしている
美しくすてきなもの
それは
恋
「私は死にそうだ!」
――文系学部の叫びに 斉藤明典
《Je suis mort!》
「私は死にそうだ!」
ロラン・バルトが躓きの石として挙げ
ジャック・デリダがそれを引用して書いた
バルト追悼の小論文 からの孫引き
この表現は 文字通りには
「私は死んでいる」「私は死んだ」
死者がしゃべるはずのない不可能な言葉
しかし フランス人の間では使われている
《Je suis mort!》
「私はもうへとへとだ(死にそうだ)!」
今の日本の政府・文部科学省による
大学・文系学部の縮小・廃止への圧力
「理工系で稼ぐので
考える人間は不要」
フランスで選挙のときに
「今さら公務員試験の問題に
『クレーブの奥方』でもあるまい」と
サルコジ大統領が発言
これをきっかけに
反発した大勢の人々が
パンテオンの前に集まって
この小説を朗読した そして
ラファイエット夫人の心理小説が
見直され 復権した
ぼくたち「文系」の中にいる詩人も!
通天閣にのぼって わたしたちにも
「活躍」する権利があると 詩を読もう
*過日近所の小さい画廊で詩画展を開いた。
終了後、見に来てくれた人に、感謝し、
贈った詩を一部追加修正したもの。
記憶の中の伝言板 山本なおこ
夜更けに駅の伝言板を見るのは
何という寂しさだろう
きっちり大きく書かれてある文字も
遠慮勝ちに小さく書いてある文字も
青白くあって
蛍が飛んでいるように見える
これらの伝言板のメッセージは
相手の心に届いたのだろうか
もしかしたら何一つ
届かなかったのではないか
朝になれば 綺麗に消されて
また人待ち顔になって立っているのだろう
それでも私は私宛に書かずにはいられない
希望をもってと 胸のなかに
ポストまでの近道 蔭山辰子
ポストはコンビニの角
隣りにはパン屋さん
向いには花屋さん
友だちの家もすぐそこ
せめて
そこまで歩けますように
それが足を痛めた
今の わたしの願いごと
柿みどりに
白い蝶 二匹
風に身をまかせて空に幽ぶ
自然は元気
梅雨も終わりの萌黄色
ポストまでの近道
君が泣いている 中島省吾
君が泣いている
イエスが泣いている
君が笑っている
イエスが笑っている
心の闇を打ち破るのは
君しだいだけど
心の闇の真実を知っているのはイエスだから
イエスの御業(みわざ)だから
サタンのいたずらに泣かないで
君をそんな悲しみにさせるのも
笑わさせるのも
時があるから
そんな時にイエスという
この世で唯一の医者に頼ろうよ
心のもやもや
何かを涙の中で考える君
ゴルゴタの丘の十字架の上で
何かを考えていたイエス
君の今を考えていた
君のもやもやを考えていた
君の涙を 悲しみの全てを考えて
お父様の神に伝えていた
今の君を
受け入れていた
今の君の悲しみの全てを受け入れていた
イエスは泣いていた
君のために泣いていた
今の君の悲しみのために涙を流していた
大胆で
悩ましくて
雑食な
今の君の不良不視の解決のための
血を流していた
痛み苦しんだ
泣いていた
祈ろうよ そんな人に
祈りの電波を伝えよう
きっと天でお父様と
「まだか? まだか?」と待ちくたびれているよ
君の解決策を用意して
待ちくたびれている
やめないでキリストを
教会を去らないで
君がいないと
寂しい
君がいないと教会がおもしろくない
なんだかんだ言いながらも
君はイエスという最高の宝物と出逢った
それが神の定めたしるしと
見るならば
君は神に選ばれた最高の人生を約束して下さっている
君の可能性は無限大
君の夢は何ですか
君の夢もイエスキリストはきっと叶えてくれるから
君の姿が見えないなんて
私に言わせないで
君がいないと私たちはとても寂しい
君の愛は無限大
最高の輝きとこの世で出逢った
私たちは最高の人生の時を過ごしているのだから
君も仲間だから
やめないで教会を
君がいないと寂しい
最高の時間を この世の時間を過ごしている
私たちは最高の人生の時を過ごしているのだから
愛の風が吹く時もあるけど
悲しみの風が吹く時もある
それも全て イエスの作用だから
受け入れようよ
あら大変 ボクちゃんが 水崎野里子
あら大変 ボクちゃんが
病気になっちゃった
入院しちゃった
もう一度
生きて街を歩けるか
みんなと一緒に
クリスマスの歌を歌えるか
なんて言ってる!
ごめんね
おかあさん
あなたを産んで
あなたを産むとき
まさかこの世が
こんなにも地獄だ
なんて考えなかった
世界中の母親の罪よ
こんな苦しみを
息子や娘に
与え続けることが
あるなんて
憎しみが 殺意が
ありふれているなんて
あなたを産む苦しみに
私は耐えた
死ぬかと思った
もう 今死んでも
あなたは生まれる
そう思った
でもこんなご褒美貰う
あなたの恐怖を
せめて抱きたい
おかあさんが
あの世に行ったらよ
雲の上でそっと
だっこしてあげる
涙であなた濡れるわよ
でもそれくらい
我慢の子
それまでは
いつものように
きちんと背広
襟を正して
ネクタイまっすぐ
目上の人には礼を尽くして
言葉使いはおだやかに
そう いつものように
毎日きちんと
生きてください
三度三度の食事を忘れず・・・
出来る限りね
コロンビーヌ 水崎野里子
私の帽子は小鳩ちゃん
端っこピョコンと
白い羽
空に向かって
ゆーらゆら
街中すいすい歩きます
毎日散歩の曇り空
私は海のお舟なの
太陽目指して
帆を上げて
意気颯爽と
大海へ
海はきらきら
金の波
眩しい光を燃やします
キャンドルライトの
ゆらめきよ
海に見えるは
小さな帆船
並んでたくさん
行列行進
いざ帆を上げて
見知らぬ国へ
ちまちま ちょこちょこ
滑り行く
私の名前は小鳩ちゃん
これから私は舞い上がる
水平線から大空へ
二枚の羽を高々と
掲げて さあ今
飛翔する
海のざわめき
打ち叩く
私の羽は
天使羽
青い大空
抱き尽くす
神々の意匠/女神のモード 葉陶紅子
星々は衣服をまとい 脳髄は
コロンをまとう 裸身の膚に
神々の男根は 薔薇色である
ロゴスの骨格が 麦酒色にしなる
鳥から孵化した太陽は 処女の唇
裸身の下は 濡れ羽色の夜
身を飾る 琥珀に閉ざされた蜥蜴
朱色の舌で 月を湿らす
天国と地獄をまたぎ 空色の
死を織りかざす 脚線のヒール
神々は歴史を拒否し 女神らは
時を棄て去り 裸線をまとう
マロニエの花咲き 葡萄青々と
裸線を飾る 太陽(ひ)と月の不死
身体としての風景 葉陶紅子
一面の曠野の素膚に 穿たれし
めくるめく刺青(きず) 幾何学文様
起伏する曠野の膚の 刺青見れば
永遠は笑む 昼空の辺より
膚に刺す刺青は 死を膚に刻みて
芯まで降りて 水を吸いあぐ
おのこらよ 大地に列びFUCKせよ
刺青ほりおこし 種子蒔きちらせ
種子はのび 丘の曠野を花やかしめん
そを膚に着て 空をゆかんか
翼とは 夜を孵化さす刺青より生えて
おのが曠野を 俯瞰する術
死と生の2つ顔して 風にのり
自由な空を 滑りたのしめ
泣くということ 関 中子
泣けるなら
泣いてみたい
泣けるなら
声をあげて泣いてみたい
涙をとめどなく流して泣いてみたい
川の源流がこんなふうに始まるよと
言えるようにとつとつと
泣いてみたい
どこから涙があらわれて
どこへ消えていったか
涙を見たのにだれも
はっきり言えないことを泣いてみたい
何を泣いたか
わからなくてもよいから
たぶん 歴史が泣いたのだろう
おそらく 地球が泣いたのだろう
それとも湖面にゆれる月が泣いたのだろう
星がちらついて風が泣いたのだろう
泣いてみよう
思ったときに
わんわん骨がしなうように泣いてみよう
裏 表 晴 静
冷気残る風うけて
さやかに開いて
秘めて匂うは
梅一輪
春出会い
暖気溢れる風うけて
華やぎ置いて
惜しまれ散るは
花吹雪
春別れ
春来て春逝く
出会い
別れ
背中合わせに
裏 表
日記 ハラキン
或る日の夜は ただただ静かで何事も無く 次に進む理由すら無く
時間が経っていく主観だけが 時間の残り滓のようにあった 時計は
止まっていた 風は吹いている風の状態で止まっていた 風に揺れた
ガスの火は風に揺れたまま止まっていた 音楽は時間が止まる直前の
音のまま止まっていた 「時間は実体ではなく 現象の変化に即して
在るにすぎない」 俺だけが動いているこの現象を書こうと日記帳を
開くと 日付の印刷がいつのまにか消えていた 最初から無かったか
のように
翌日の日記を 前日に恣意的に書いたら 翌日に 書いたとおりのこ
とが起こった 未明にすさまじい落雷があったこと 昔の恋人に出く
わしたこと 俺が書いたとおりのことが起こったのに 問題にはなら
なかった 俺の恣意が実現したのか いやじつは俺の恣意ではなかっ
たのか 「あらゆる存在は心にすぎない」「この三界はただ表象にす
ぎない」 心臓が止まるほどの落雷 ほぼ同時に 無数の滝のような
雨が 世界の汚れを洗い流してくれたあげく 早朝の陸橋の上 昔の
恋人がむこうから歩いてきた 映像のように
母なるもの ハラキン
(継母)
「あんたなんか死んだほうがええ」
小さなしかし確かな声を浴びて
小学生の男児は
ズボンのポケットに手をつっこむ
声の毒がただよう家屋の廊下
陽射しは明るい
放課後
そうじする児童たち
「おとなの女の人があんたに会いに来てる」
女児にいわれて
男児はなぜか誰かがわかった
跳び箱の倉庫の片隅
着物姿の生母
菓子折りをもっている
男児の名を呼んだ
そうじのノイズが大きくなる
三歳の男の子の視界
そばにいる祖母
玄関先に
しばらくいなくなっていた生母が
知らない中年男といっしょに
家出のあいさつに来ている
さらに幼い男の子が
祖母の乳房を吸っている
母なるものの愛情が
どんなものか感覚できない
生の
重要な部品が無い
郊外の駅の脇に
はびこるセイタカアワダチソウが
秋風に
いっせいに揺れる
蟬か人か ハラキン
樹の枝につかまって
それは
脱皮しようと蠢いていた
蟬のようであり
人のようでもあった
このたびの生
の男Aは
みずからをなげうって
着衣の岩になったり
生臭い書物になったり
なにごとにつけ
おのれを展示しようとした
次の生
では女Bになるらしい
陰気な性格のあまり
保護色を身につけ
気配を消すこともできるという
演歌が遠雷のようだった
工事音が銃声のようだった
カラスたちの会話が続いた
役所のスピーカーから
古い経典が読誦された
脱皮するなら今だ
男Aは
樹の枝につかまって
先ず顔の皮を裂いていった
裂け目から
Bの顔があらわれた
人のようであり
蟬のようでもあった
自分 神田好能
つらさというものは
自分にかえってくる言葉なんだ
それが判ってからでも
何年にもなるのに
こりもせず 過ごす時間
それでも生きているかぎり
自分の時間は自分で
過ごすことしかないのだもの
老人ホームへ入所
一人きりの時間は変わらない
でも何人もの友人があり
それは嬉しいことになった
時々同じような淋しさを
かかえている人もありで
瞬間嬉しいなぐさめと
なっている
夕影草 本多清子
透明なみずあさぎの空に
白い夕月
五色の雲に囲まれて
大空に
夕影草が 咲いた
いっぱい 広がる
その茜いろ
山の稜線を 染め
わたしの体を染め
わたしの心も染め
最後に もう一度
明るく燃える
夕日の 光芒
なまけもの 根本昌幸
なまけもの
と いう動物は
木の枝にぶら下がっている。
ゆったりとした
動作で。
あれではほかの動物に
やられてしまう。
だから木の枝にいるのだろう。
なぜだか
おれもあのなまけもの
と いう動物に
似ているような気がする。
近頃のことだが。
年令のせいか。
それとも違って
もともとそういった
性格だったのか。
分からなくなってしまったが。
ゆったりとした
動作になった。
いろんなことが
面倒になった。
なにもかもが
いやになった。
これを
なまけもの
と いわずに
なんといおうか。
なまけものは
木の枝にいる。
おれは家の中にいる。
ごろごろして
なにもすることがなくて。
〈シリーズ・手〉伝言 原 和子
革の手袋の片方は
ただ 落ちているだけではなかった
拾い上げるにしては
あまりにも 重過ぎた
生身の 五十男の掌が
敗北した
冬の残骸を 摑んでいた
脂じみた
縦横の皺に走る
奇妙な 伝言
すばやく読み取って
公園裏の 寒々と立つ街路樹を探して
ひっかけると
ぶらり、とぶら下がった掌は
気の弱い 自殺者のように
背後から
私を 追い立てた
深夜 原 和子
日が昏れる
立木は ざわめきの口を閉ざし
放置自転車のハンドルに
わずか 昏れ残る 光
やわらかい生きもののように
地上に降り立つ 夜
深夜
道端で死んだ 人間や
人間のこども 犬や猫たちが
いっせいに立ち上がって
血まみれの腕で
夜の深さを測り
泣き崩れるとき
車は けたたましく軋んで
また 何かを轢き殺していく
小詩篇「花屑」その8 梶谷忠大
もし 野山に在れば
坂の上方に 四方八方へ太い枝を張り
坂下の 通学路にまで小枝を伸ばしている
せんだんの樹よ カンダタの樹よ
風の吹く日 羽状の葉がとび散る
北風の吹き荒れる日 葉を失った葉柄が降る
くる日も くる日も 坂につもる
葉を掃き集め 柄を掃き集める
くる日も くる日も 通学路につもる
葉を掃き集め 柄を掃き集める
寒風が 吹きすさぶ日
金鈴子という美しい名を持つ せんだんの実が
坂に 落下して ころがる
坂をころがり 通学路にたまる
せんだんは 裸木になるまで
葉を 柄を 実を 落とし 落としつづける
葉は 柄を 金鈴子は 掃かれ 捨てられる
せんだんの樹よ カンダタの樹よ
もし 野山に在れば
地を肥やし 土に埋もれ 芽ぶき
芳しい双葉が 空にむかって 両手を揚げただろう
見上げれば のこる金鈴子が
虚しく日に かがやいている
遠きもの近きもの 梶谷予人
はつなつの骨模型立つリハビリ室
舞鶴に軍靴の空音凪の海
語り部の三打の鐘や月見草
いさかいの国境いくつ水澄みぬ
夕焼けて鴉騒がしガザ・カナン
難民に汀は暮れて赤い月
生き物 日野友子
私は私の命を
何かのひきかえにしたくない
私はノロマな いち生き物である
私はこの時代を右往左往する
市井のいち個人である
私の死を悲しむのは私の知人まででいい
私のために祈るのは私の家族だけでいい
まちがっても 世界の人とか エライ人とかに悲しんだり 祈ったりして欲しくない
私はテロで殺されたくない
私は空爆で殺されたくない
私は壮大げな何かのために殺されたくない
私がいち生き物であることにかけて
貴方がいち生き物であることを尊重させてくれないか
食うこと 排泄すること 清潔であること
眠ること
日々の安全
私や貴方に大事なのは そのことだろう
命で購えるものは ない
爆弾で時代に風穴はあかない
時代とは つまるところが いち生き物が絡みあって紡ぐものだろう
思い出そう 自分がいち生き物であることを
他の何にもなれないことを
霙降る日の 左子真由美
何もかもうまくいかない日がある
少なくともそう思えるときがある
霙が
灰色によどんだ空から
冬の終わりの街に降る
仕事を終えて
ひとり歩く舗道
ふと見上げた眼に
桜並木の
裸の痛々しい枝に
霙に打たれている
ほのかに膨らんだつぼみ
凍てつく寒さの中で
確かに咲こうとしている
そのいくつものつぼみの愛しさ
私は足を止めて
じっとつぼみを見つめ
それからまた
人の流れに混じっていく
それが何であろう
ささやかな営みの
うまくいくとかいかないとか
霙に濡れて
手足が凍えても
それが何であろう
生きることが
こんなにもいじらしくつつましく
確かであるのならば
私はそのことを誰にも言わなかった
その日の言い知れぬ感動を
いや、誰かへの手紙の最初の挨拶に書いたかもしれない
――桜のつぼみが膨らんできましたね