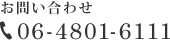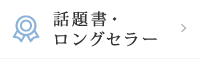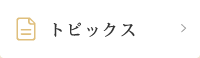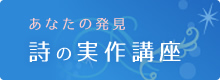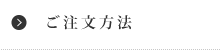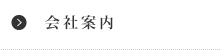![]()
トピックス
2019年09月16日
☆左子真由美詩集『RINKAKU(輪郭)』が9月16日付京都新聞「詩歌の本棚」の欄で、紹介されました。
☆左子真由美詩集『RINKAKU(輪郭)』の書評が9月14日付「図書新聞」に掲載されました。こちらからご覧ください。
カテゴリー:ニュース
--------------------------------------------------------------------------------
☆左子真由美詩集『RINKAKU(輪郭)』の書評が9月14日付「図書新聞」に掲載されました。
☆2019年9月14日付け図書新聞より
私たちを取り囲んでいる
さまざまな「さかいめ」の存在
人が記憶として覚えていることは、ほんの上澄みだ
寺田 操
◆左子真由美詩集『RINKAKU(輪郭)』
2019.7.14刊 A5変型判80頁 本体1800円
黒の地に白い線画、パウル・クレーの絵のような柔らかい曲線使いのカバー絵(美濃吉昭)の帯に一篇の詩が白字で刻まれていた。
「それは/パンの竃(かまど)の小さな種火/遠い昔に/消し忘れたままの/部屋の灯り/いつまでも/いわれのない懐かしさと/寂しさで/わたしの肩をたたく/愛しいシグナルよ//あなたはだれ?/だれの指?」(「シグナル」)
ふいに明かりを落とした小さなステージに誘われ、遠い日にライブハウスで聴いたシャンソンを思い出した。一人の詩人が歌うように静かに詩を語っている。初冬のパリ「カフェ・プーシキン」で見た年老いた男女の物語を、パリの路地裏で風船を売る「マリアンヌ」のつぶやきを、戦場の血の記憶を流す「この雨」のことを。
シャンソンは「三分間のドラマ」といわれる。過ぎてきた日々の陰影を幻燈のように映し出すかと思えば、エスプリの効いた語りを未来へ向けて響かせる。「シグナル」は人生の交差点の信号であると同時に、世界を照らす小さな「徴」ではなかろうか。
「りんごをなぞるように/きみのりんかくをなぞる/ふしぎだ/せかいと/きみとに/さかいめがあるなんて」(「輪郭」)
目の前にいる誰かの顔をスケッチしているのか、それとも記憶のなかの誰かを思い浮かべて描いているのか、あるいは愛しい人の顔に手を伸ばして皮膚に触れているのか、さまざまな想像をかきたてる詩である。気づかされたのは、過去と未来という時間軸もふくめて、私たちを取り囲んでいるさまざまな事象や関係性についての「さかいめ」の存在である。さかいめ=境界は、明確な輪郭をもって発語可能な対象として出現するわけではない。ぼんやりと、とぎれとぎれにしか姿を現さないし、時には輪郭を溶かし、消してしまうことだってある。厄介なのは人と人とが明確な輪郭を持って関係を結ぶかといえば、そうとはいえないことにある。
「シグナル」と「輪郭」の二篇は、詩集全体のキーワードであると同時に「喩」でもあるのだろう。世界とわたしの、わたしとあなたの、昨日と今日の、今日と明日のつなぎ目。心の襞に覆い隠された記憶のときが、どのようなきっかけで照らしだされるのか。詩集の誕生についての「物語」をたどってみたい。
記憶がくっきりとした輪郭をもって浮上してきた「ドナウ河の漣」、「ローレライ」、「美しく青きドナウ」に強く惹かれた。どの物語も読み手が、「まるで私の物語のようだ」と郷愁を呼びこむ散文詩だ。ここでは「ドナウ河の漣」を読んでみたい。仕事帰りの電車の窓から見えた、真夏の日暮れ前の虹。車内を見回すと虹を見上げている人などいない。ふいに胸のデッキから懐かしい歌が流れてきた。小学生のころ、若い日の母が台所でよく口ずさんでいたメロディーだ。事業に失敗した父、次々と家族を襲ってくる不幸な出来事。そこだけが「空白」となってしまう弟の死。「モノクロの映画のワンシーンのように頭の隅に残っているだけ」になってしまった家族の生死を、記憶の匣から呼び出したのは、母が歌う声、哀愁を帯びた美しい調べだった。
「それは/いつどうやって/わたしのなかにやってきたのか/だれかがきっと/詩というちいさなたねを/なげいれたにちがいない/どんどんおおきくなって/からだのなかにしずんでいる/おもいおもいいしのようで/はやくでていいてくれとねがうのみ/けれど/ことばというつばさを/うまくつけると/それはかるがるととんでゆく」(「事件」)
核心をついた作品だ。自己表出を試みても、ぴったりとした「ことばというつばさ」をつけられるとは限らない。ちいさな種がまかれた土地を耕し、土壌を潤し、手塩にかけて育てなければ実は成らない。人が記憶として覚えていることは、ほんの上澄みだ。深層に眠っている澱や、穴ぼこだらけの思い出、眠りからさめない体験などを、発語の縁へそっとひきあげていく、その器こそが詩なのだ。
(詩人)
※図書新聞様の御厚意により転載させていただきました
アーカイブ
- 2026 年 2 月 (1)
- 2026 年 1 月 (1)
- 2025 年 12 月 (1)
- 2025 年 8 月 (1)
- 2025 年 6 月 (1)
- 2025 年 5 月 (1)
- 2025 年 2 月 (2)
- 2024 年 11 月 (1)
- 2024 年 8 月 (1)
- 2024 年 7 月 (1)
- 2024 年 5 月 (1)
- 2024 年 4 月 (1)
- 2024 年 2 月 (1)
- 2024 年 1 月 (1)
- 2023 年 11 月 (2)
- 2023 年 8 月 (1)
- 2023 年 7 月 (1)
- 2023 年 5 月 (1)
- 2023 年 3 月 (1)
- 2023 年 2 月 (1)
- 2022 年 11 月 (2)
- 2022 年 8 月 (1)
- 2022 年 5 月 (1)
- 2022 年 2 月 (2)
- 2021 年 11 月 (1)
- 2021 年 8 月 (2)
- 2021 年 5 月 (1)
- 2021 年 2 月 (1)
- 2021 年 1 月 (1)
- 2020 年 12 月 (1)
- 2020 年 11 月 (1)
- 2020 年 8 月 (2)
- 2020 年 5 月 (1)
- 2020 年 4 月 (1)
- 2020 年 2 月 (3)
- 2019 年 12 月 (1)
- 2019 年 11 月 (1)
- 2019 年 9 月 (1)
- 2019 年 8 月 (1)
- 2019 年 6 月 (1)
- 2019 年 5 月 (1)
- 2019 年 3 月 (1)
- 2019 年 2 月 (2)
- 2019 年 1 月 (1)
- 2018 年 11 月 (1)
- 2018 年 10 月 (2)
- 2018 年 8 月 (1)
- 2018 年 7 月 (1)
- 2018 年 6 月 (1)
- 2018 年 5 月 (1)
- 2018 年 4 月 (1)
- 2018 年 2 月 (1)
- 2018 年 1 月 (1)
- 2017 年 11 月 (3)
- 2017 年 8 月 (2)
- 2017 年 7 月 (1)
- 2017 年 5 月 (1)
- 2017 年 4 月 (1)
- 2017 年 2 月 (2)
- 2016 年 12 月 (4)
- 2016 年 11 月 (1)
- 2016 年 10 月 (1)
- 2016 年 6 月 (3)
- 2016 年 5 月 (1)
- 2016 年 2 月 (1)
- 2016 年 1 月 (1)
- 2015 年 12 月 (1)
- 2015 年 11 月 (1)
- 2015 年 10 月 (3)
- 2015 年 9 月 (1)
- 2015 年 8 月 (2)
- 2015 年 7 月 (1)
- 2015 年 6 月 (3)
- 2015 年 5 月 (1)