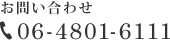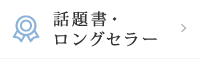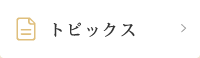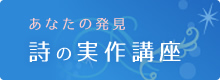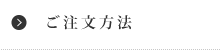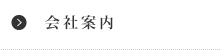![]()
181号 犬と猫
181号 犬と猫
- 円卓 金田久璋
- 寒の夕ぐれ 山本みち子
- 再訪 伊藤浩子
- 女 女 女 方韋子
- 気をつけ 佐々木 豊
- そう言えば 佐々木 豊
- 牧歌的な一品 佐倉圭史
- 海へ 西田 純
- 生かされて 平野鈴子
- 頬づえ 平野鈴子
- お針の技量 平野鈴子
- Wating 4 Stars 2 Fall 葉陶紅子
- 日々のはて 葉陶紅子
- どうします? 白井ひかる
- コロナウィルス 牛島富美二
- 演技なるもの ハラキン
- 左手薬指の爪 ハラキン
- ノンフィクション ハラキン
- 跳び箱の倉庫 ハラキン
- 演技の洞窟へ ハラキン
- 小さな飛行機 笠原仙一
- 新しい時代 笠原仙一
- 腹と背中 吉田定一
- ウミガメ 根本昌幸
- わたしの胴体はどこへ 牛田丑之助
- 一両編成 牛田丑之助
- 気づくと私はベッドの上にいた 牛田丑之助
- 前夜 牛田丑之助
- 傘 来羅ゆら
- 人生病 吉田義昭
- 渡り鳥から人間さんへ 阪南太郎
- 歌う理由 加納由将
- 仏法真理 中島(あたるしま)省吾
- 生を受けて 中島(あたるしま)省吾
- その「ステージ4」にて 下前幸一
- <PHOTO POEM>昔日 長谷部圭子
- <PHOTO POEM>僕の相棒 中島(あたるしま)省吾
- マリアンヌ ―歌のために 左子真由美
- 待つ 中西 衛
- アスリート 卓球 中西 衛
- 真っ正直にすわってみる 山本なおこ
- 光 水崎野里子
- 歌を歌いたい 水崎野里子
円卓 金田久璋
息を吹きかけハンコを押す
印鑑がかじかんでいる
人差し指の骨を削るように
武骨な震える手で
血判を捺して 必死に村を守ろうと
一揆に立ち上がった
先祖たちの傘連判に
霙が降りかかる
よこしなぎに 時には
ひたむきに時代に向き合い
平穏に時が過ぎゆくのを
待ちながら 過ごす日々が
今は核の傘という連判状に
いつしか連座され
お白洲に引き出されるやも知れず
囲炉裏やちゃぶ台の円卓が
いつしか消えた頃から
世間のなりゆきが不穏になって
固いテーブルの一角に ひとり
置き去りになる 聳つ断崖
途方に暮れて むしろ
尖ったロケットのかわりに
鉛筆を届けたい 棘を逆立てて威嚇する
居丈高な寒い国の 飢えた子どもたちに
どっさりと 虹色の 橋を渡って
*『東京新聞』2017・10・28夕刊文化欄掲載作品を一部改稿
寒の夕ぐれ 山本みち子
寒の日ぐれは きまぐれよ
風に追われた はぐれ雲
名残惜しげに 逃げてゆく
鳥になり 魚(うお)になり
ときには 大きな鯨となって
小魚の群れを 飲み込んでゆく
それに ときには
頬の紅い少女が 金の冠をいただき
白馬の背なに揺られて 遠ざかる
おや? 誰かに呼ばれたような……
茜の空をふりあおげば まだ若い母が
生まれなかった弟を抱き 乳をふくませている
思わず腰を浮かせかければ
ふたりは ほったりと燃え落ちる夕焼けに染みて
母の声だけが 風に混じって聞こえる
《待っているよ ゆっくりおいで》
再訪 伊藤浩子
噎(む)せ返る翠(みどり)の溜息に足もとを取られながら歩いた。
すべての影はひっそり消え失せ、丸く縁取られた暗い空を尾の長い鳥
が嗤いながら渡っていく。
破れた群青を縫うように、庇(かば)うように、雲も薄く犇(ひし)めいて、季節の疵
口をそのまま抱きしめている。
いったい幾つ乗り越えてきたのか、苔に塗(まみ)れた濡れた岩肌を眺めなが
ら、次第に広がる星空をメロディにして耳の底で聴いている。
約束は風になり、言葉もなく、輪郭もなく、その人の胸に届けられる
黎明を、既に悴(かじか)んだ指先は予感として孕(はら)みつつ、背後にも白い糸を引
いて伸びてゆく。
彼方にあるのは涙雨の湖、無数の死児が待ち侘びているから、今夜も
先を急がねばなるまいが、時の推移は呼び声を翳(かす)め、足蹠を土に埋め、
惑わせるように樹木を集める。
立ち止まってはいけない、振り向いてもいけない、やがて昇る不実な
月の盈(み)ち虧(か)けさえ拒絶したなら、ひとつだけ息を吸い込み、新しい一
歩をまた踏み出した。
途中で別れた者の名と記憶を交互に、くちびるに灯りにしては古道を
照らし、地図もなく、道標も倒れ、帰り路も覚束ない、ここは北の最涯。
なつかしい花の匂いが鼻を掠める。
脱ぎ捨てられた昆虫の夢の亡骸が腐っていく音が折り重なる。
梢の啜り泣きは祝祷(しゅくとう)に変えられていく。
根雪は過去の徴として点在している。
覆い被さる嶮しい山影のもと、幽かな温みを貧しい毛布にして肌に纏(まと)
い、また歳を取った。
額をつたう碧い汗と、翅をもがれた背中と、血の滲んだ踵と、両膝の
瘡蓋(かさぶた)と、深く刻まれた皺の余波とを脱ぎ棄て、遥か解けるように、い
つかの森の一部になっていく。
女 女 女 方韋子
(1)傲岸な女
ゴウガンの「傲(ごう)」と「岸(がん)」
どんな荒波にもたじろがず
跳ね返すような頑なさを表している
モスクワのトレチャコフ美術館にある
「見知らぬ女」という絵画
帝政ロシアの時代のもの
わたしの便箋の裏に印刷されてある
美術館の名前も画家の名前も知らない
はじめてお目にかかる絵
「見知らぬ女」は
馬車の背にゆったりと腰を落ち着け身体を沈め
「フン!」という顔つきをし
馬車を見上げる私のことを見下げる
白い大きな羽根飾りをつけた 黒い帽子
黒ずくめのショール・カラーに
きりりと身をつつむ 小顔の美人
私と目が合ってもたじろぎもしない
鼻は上を向き 見返す目は鋭くゆるぎがなく
目と鼻は一体となって頑なさを表す
人を人とも思わない
「早く道をあけて! ひき殺すわよ」
と いわんばかり
(2)マリー・アントワネット
マリー・アントワネットは
大衆の怒号のなか ギロチンにかけられて死んだ
ちょうどこの日 彼女は月のものであった
アントワネットは刑場の広場に引立てられるとき
王宮の板のやぶれ目に 下着を押し込んで隠した
王女の身から出た錆によって民衆の怒りをかった
のだが 冷静に自分を見失うことなくあっさりと
首を落された
可愛くない女の最期らしい最期 であった
王女はもっとも人間らしさのなかで死んだ
それだけといえば ただそれだけ
(3)智恵子
室生犀星は貧しい下宿住まいと高村光太郎のアトリエとを
比較して 自分のみじめさを知るにおよんで がぜん光太
郎を訪問すれば救われるように思い描いて出掛けていく。
光太郎とは初対面であった。
犀星は書いている。
まだ小説家としてうだつの上がらないころ原稿を持って
どこかに紹介してもらおうと有名な作家を訪ね回ってい
た。ある日 高村光太郎宅を訪問し 私はおそるおそる
その呼び鈴を押した。
一分三十秒ぐらい待った。 やがて小窓の内側の
カーテンがさっと怒ったように引かれた。すると小窓一
杯にあるひとつの気取りと冷淡とバカにしている目付き
に出会った。私は 高村さんは今日はおいででしょうか
と おずおずとしながら来意を言った。するとこの女は
軽くあごを下の方に引き 来意を知ったふうを装い
さっとカーテンを引いた。
再びカーテンが引かれ ツメタイ澄んだ大きくない一重
瞼の眼で 上唇で圧迫したような語調でいった。
「たかむらはいまるすでございます」
(居留守をつかっている――と犀星は勘繰(かんぐ)った)
「いつごろおかえりでしょうか」
女の眼はまたたきもせずに私を見たまま
「わかりません」と答えた。
私が頭を下げるとカーテンはさっとハリガネの上を吊り
環をきしらせてまた走った。
再度訪ねるとまた女が顔だけを出して
「たかむらはただいま出かけて居ります」
と同じ返答をした。
私は名前を告げたが 彼女は「あ、そう、ふん」という
ふうに言ってカーテンをまたさっと引いた。
ツメタイ眼は夫のほかの者を見るときに限られ 夫には
忠実で ほかの者にはくそくらえという目付きでやはり
追い払った。このツメタイ眼がツメタイために美しく映
じているのを怖れた。 この女のひとこそ
『智恵子抄』の智恵子であった。
と書いている。(*)
光太郎が描く智恵子とはほど遠い智恵子
光太郎の智恵子は 生れたままの智恵子
穢れを知らぬ 純粋で 弱々しい智恵子
犀星は嘘は書くまい
犀星の書く智恵子も
また智恵子であった
智恵子は 原稿を小脇に抱えて現われる
売れない小説家の卵を 胡散臭い
こうるさい奴ぐらいにしか見ていなかった
智恵子は彼らをツメタイ眼で押しかえした
犀星は一分三十秒ぐらい待った
この微妙なはかったような時間の現実
この一分三十秒という長さ
この一分三十秒を長いと見るか 短いと見るか
女はおそろしくもなれる
*室生犀星『わが愛する詩人の伝記』講談社文芸文庫
気をつけ 佐々木 豊
家の裏の空き地の塀を背景に
「気をつけ」をした手は
入学式で着た半ズボンの横に
ぴったりとくっつけられている
62年たった今も
ボクの手は
「気をつけ」をしたまま
そう言えば 佐々木 豊
ボクが弁当を慌てて食べるようになったのは
伊勢志摩への修学旅行に遡る
宇治山田駅からバスで外宮へ
ボクはバスを見ただけで酔う子だった
酔い止めのため乗車するとすぐに目をつむる
ボクはバスの車窓の景色を見たことがない
お伊勢さんにもバスにロープを括り付けて
ロープに引っ張られて走って行きたいと思っていた
セーターの下に入れて行動していたお弁当を雨に濡らしてしまった
毛糸まみれになったお弁当を食べられなくなって
内田先生とレストランで食事をとった
特別の場所で
大好きな内田先生と
二人で食事をすることになった
友達にそんな様子を見られるのが嫌で
急いで食べたんだ
今日は大学入試で出勤
お弁当がでた
研究室でひとり お弁当を食べる
誰も見ていないのに慌ててお弁当を食べる
爺さんになっても食べるお弁当の食べ方は
そう言えば
五十七年前の修学旅行の時の
雨に打たれたお弁当の代わりに
内田先生と二人 レストランで食べたときの食べ方と同じ
牧歌的な一品 佐倉圭史
林立する高層ビルのほんの傍らに
林が―「矛盾林」―が存在する
「全くの無名な林である」
知るのはせいぜい二人か三人で
彼等は入っていき、読書か何かをすれば
思考が美しい変転を来す
まるで窓ガラスに付着した水滴――
光の加減で覆う色彩を変える、透明人間達
海へ 西田 純
潮の音 波の太鼓を 胸に聴く
今年は 何度 海に会えるのか
旅に出ると 自分の体が 宙に浮く
心だけの 重さになる
せまい路地 いくつも曲がり 迷い込む
海は たしか こっちのほうだが
海を見る あまりの広さに ぼくは消え
時間だけが 空をさまよう
いつまでも話していたい 夜の海と
沖の舟の 光が沈む
夜の海 見えない鏡の静けさの
底に沈んだ ぼくの残骸
灯台の 空を突き抜け 延びていく
青いかなたへ 走っていこう
生かされて 平野鈴子
静まりかえった深夜
ブラインドを開ければ大パノラマが広がる
月あかりに満天の星がキラリ
山なみの送電線の鉄塔が
赤いルビーの煌めく点滅をくりかえす夜寒(よさむ)のとき
第二京阪に点描画のようなライトが走る
交野の山の稜線のむこうから
あけぼの色がかすかに色づく
刻一刻と変化する神々しいほどのご来光
まるで名刀の湾(のた)れの美
魂まで清められ ただ立ち尽くす
術後の朝
ゆるやかに柔らかな陽が差し込んでくる
川辺ではヨシやガマの間からゴイサギが
水面(みなも)を見つめている
そして
朝な夕なの営みがなかったかのように
西の山かげに夕陽がしずみ
ゆったりと一日が過ぎていくのだ
あすも生きる
わたしは生かされている
頬づえ 平野鈴子
カーテン越しにさしこむ朝のひかり
テーブルには昨夜作ったピクルス
お母様の介護生活も何十年でしょうか
仕事との両立
三ヶ月ごとの病院探しに翻弄された時間
胃ろうまでされたが力つきた
ぷっつり切れた糸をどう結びなおすのか
「母の年金が打ち切られた」の声がまた悲しい
父の娘でよかった
母の娘でよかった
の孝行娘がおひとりさまになってしまった
身を固めるひまもなかった彼女
今還暦と知る
モザイク状にぎっしりつめこんだ
大根・人参・胡瓜・ラディッシュ・ペコロス(*)・カリフラワー・カブ
スパイシーなピクルス液には
丁子・ニンニク・ローリエも入れてみた
ピンク色に仕上がり
はじらう少女のように頬をそめている
日曜日のブランチは
厚切り食パンにキーウィジャム
生ハムとコーヒーの香りがたつのが私流
テレビを消し
朝刊を広げるときめきの至福のとき
ゆったり時のながれをたのしみたい
頬づえをつき
食べ頃のピクルスのビンを見つめながら
「仕事帰りに取りに来て」の手紙に今夜もまた
チャイムはならない
中原淳一の絵のようなあなた
「ひとりじゃないよ」と発信しつづけている
*ペコロス 小玉ネギ
お針の技量 平野鈴子
布団屋から打ち直しの
ふかふかの綿が届く
袷(あわせ)の膝の抜けた大島紬を
掛け布団に仕立て直す
くけ台をさし込み
針山は髪を赤いモスリンの布に入れ
木綿針・絹針・紬針・くけ針・待針・布団針・手糸針がさしてある
傍(かたわ)らに革(かわ)や金属の指貫が用意され
綿ぼこりよけの姉様冠(あねさまかむ)りをし
八帖間にふとんがわを広げ
手際よく綿を入れていく
四ツ折にし表に返す
見事な手さばき
まるでマジックを見ているようだ
ブルーの綿糸(わたいと)で四隅をとめ
綿が動かぬよう
何ヶ所もとめる作業
大正・昭和・平成を生き
お針の技術の高さを誇っていた
何をしてもそつがない
唯の一つも母を越えられない
恥ずかしさにうなだれる
日常の営みであった針仕事
和装文化も衰退し
針が持てなくても恥じることもなく
生活ができるいま
Wating 4 Stars 2 Fall 葉陶紅子
嵐去る 硬き乳首を愛(かな)しむごとく
驟雨に打たれ 影を砕きぬ
朧なる8月の月 うち眺め
汗ばむ肌に 星墜つる待つ
星は墜ち裸身を射抜く 内に棲む
3女人らの 臓腑を燃やし
なが内ゆ 女人3人歩み出す
蝶の憂い肌 裸身のままに
なが内に生う木の枝に 墜ちし星
懸かりて 青き木の実とはなる
この惑星(ほし)の自転を見つつ 寝(い)ぬりなば
明けの裸身は 永遠(とは)孕むべし
なが内の青き木の実を 啄ばみて
鳥よ運べや なれが分身
日々のはて 葉陶紅子
集まりて われをつくれる粒子らが
散りて宇宙(コスモス)の 無辺飛ぶ日を
宇宙(コスモス)の闇に弧坐して 植物へ
はて鉱石へ 同化する術
名で呼ぶな すべての意味を消しさって
無機物の肌 まとうは裸線
寝入りばな 恍惚のほてりの中に
沈むごときか 最期の日とは
結ばれて なが胎内に生(あ)れしより
幾多の契り 目なざしのシャワー
名利すて 毀誉褒貶の世に在りて
慈しむもの 胸に抱くもの
おのれ断つほどの苦渋を 頬に笑み
すべてのことに 辞儀できる日を
どうします? 白井ひかる
──先ずは性別ですが?
カウンセリングが始まった
──女の子でお願いします
夫は落ち着いた様子できっぱり答えた
長い間夫婦ふたりで話し合ってようやく決めた結論だ
──成人になった時の身長と体重は?
──165センチ、50キロでお願いします
──髪質と肌の色合いは?
──艶やかな直毛で色白で
妻は間髪入れずに答えた
──顔立ちはお好きなタイプをお選びいただけますが
グレードにより料金が違ってまいります
偏差値によりますが70ともなりますと…
かなりお高くなります
目の前のモニターにはずらっと目の覚めるような美人の顔が映し出され
各々にランク別の料金が示されていた
妻は夫との間に予想される子どもの顔立ちをベースにして
いま爆発的な人気のアイドルスターの特徴も取り入れ
最高グレードの偏差値80を選んだ
──次は知能指数ですが いくらくらいをご希望ですか?
当然ながら高くなるにつれ料金も上がります
ちなみに理論物理学者のホーキング博士は160です
──(ホーキング博士ほどは要らないか…)
150でお願いします
──性格はどうなさいます?
──思いやりがあって優しくて
──かしこまりました
以上をもちましてスタンダードプランのお申込みは
すべて終了いたしました
カウンセラーはにこやかな表情でさらに続けた
──さて ここからオプションに移らせていただきます
当ブリリアントデザイナーズベビー社が
長年研究に取り組んでまいりましたオリジナルなクリスパー(*1)によって
誕生予定のお子様に将来のご職業に直結する特殊才能を付与するゲノム編集に
このたび100パーセント成功いたしました!
もちろん料金はお高くなりますが ご希望はございますか?
──そうですね…
夫と妻は思わず顔を見合わせ 目を輝かせた
──マリア・カラスの美声を持ち
クララ・シューマンのように甘美なピアノを奏で
マダム・キュリーのように人類に貢献できる成果を残せる科学者を希望します
──やけに盛り沢山ですね
カウンセラーは白い歯を見せニヤリとした
──それではご希望を踏まえまして近日中にお見積書を作成いたします
計画は滞りなく完了し やがて分娩の日を迎えた
ところが出生直前の赤ちゃんのゲノム解析をしたところ
大金を投じて希望したゲノムには程遠く
全くデザインされた形跡がなかったのだ
──これはいったいどういうことなんですか?!
分娩室横の控室にいた夫はカウンセラーのアバターに語気強く詰め寄った
──実はですね…
アバターは表情一つ変えずに続けた
──お客様のご注文時と時を同じくしてシンギュラリティ(*2)が勃発しまして
お客様のご希望は他のお客様にも人気が高く多数重複したため
このシステムを統括するAIが社会全体の程よいバランスを取るため
お客様のご希望は却下されたようなのです
ですので…
ここまで言いかけて突如アバターは消え
モニター画面は真っ暗になった
その頃分娩室では
元気な男の赤ちゃんの産声が
部屋中に響き渡っていた
*1 あらゆる生物のゲノム編集が可能となる技術
*2 急速に進化したAIが予測できないほどの社会の変化を引き起こす技術的特異点
コロナウィルス 牛島富美二
(一)
啓蟄の日なれど
ヒトのコロナ蟄居はまだ続くだろう
ワクチン接種が一つの目安
―立春も蟄居畑に蟇蛙―
(二)
感染者とうとう1億人突破―死者200万人超
世界14位のエジプトの人口に匹敵
日本人口に並ぶのは32日後か
―コロナ後の花見の宴期待せん―
(三)
止めて止まらぬ―収束せずという学者あり
止むならコロナ世代という語出でん―倒産・廃業・欠婚…
「コロナ」という季語は無季か
―八十過ぎてコロナ蔓延寝正月―
(四)
神に祈っても終わらぬコロナ
マスクして相手の顔も人種も識別できぬ人間疎外
コロナはこうしてヒトを滅亡させるのだ
―じわじわと感染患者増やしつついずれこの星覇者にならんと―
(五)
廃業・休業・減額・失職
鬱病・対人恐怖症・失語症
コロナの人間あぶりだし
―夕暮れて氷雨に躍るひとりの子―
(六)
自粛・蟄居・閉じ籠り…
挨拶の仕方を忘れ失語して会話中断
相手の顔を忘れていたことに気付く
―かかるまでコロナ居座る秋深し―
(七)
コロナ世代という語が造られん
オンライン・リモート・ソーシャルディスタンス
そして政府にデジタル庁新設―日本語崩壊
―なによりも入学すれど授業無し友人出来ずパソコン出来ず―
演技なるもの ハラキン
その惑星の人類は 地球の人類にそっくりだった。いく
つもの国家があり 国境もあって 武器も持っていた。戦
争もするという。動植物も似ていた。人類は酒も飲んだ。
酒場もあった。
とある酒場に入った。客でごった返していた。ビールは
無く 濃いリキュール類しかなかった。品揃え以外は地球
と同じだなと思っていたが なにか違う。なにかが大きく
違うと感じた。大きな声を出す酔客がいないのはさておき
笑い声というものがまったくなかったのだ。隣で飲んでい
た見知らぬ男に 「飲みながらジョークをとばしたりしな
いのか」などと聞くと 「ジョークってなんだ?」「なん
で笑い声が聞こえてこないんだ?」と聞くと 「笑いって
なんだ?」。
「笑いのない人生ってつまらなくないか?」「あんたが何
を言ってるのかわからない」
笑うという現象が無く 人間関係の潤滑油も不要。言葉
を交わしていても 粋なことをしゃべろうとか カッコつ
けようとか まるでない。すなわち演技というものが感じ
られない。
テレビは酒場にもあったので 「どんなドラマを観てい
る?」と聞くと 「ドラマって何だ?」「演劇って好き
か?」と聞くと 「演劇って何だ?」「ではこの星の人類
は演技というものをしないのか?」
当然 究極の答えが返ってきた。「演技って何だ?」
なぜ人は演技をするのか。というおそらく埋蔵量が無尽
蔵のテーマで詩篇を開発してきたが 笑わない。ドラマと
いうものが無い。演劇が無い。演技というものが無い。と
いう無い無い尽くしになると 詩が成立しなくなった。な
ぜ人は演技をするのかというテーマも この星では晴れ晴
れと瓦解した。
左手薬指の爪 ハラキン
六十代後半の男が 書斎の窓辺にいる。左手の指五本か
ら薬指の爪にズームアップ。爪中央にタテに折れ目の筋が
走る。つまり薬指の爪を左右二面に分けている。この意匠
のような爪は六十数年続いている。
六十数年間 この爪のことを前向きに考えたことはなかっ
たが ほんの数ヵ月前 はじめての価値観が降りてきた。
その男児は一歳か二歳か まな板の上で何かを包丁で切っ
ている生母のそばにいる。
何かのきっかけで 男児が左手をまな板にのせた。たぶ
ん素早く。生母の包丁は 男児の左手薬指の先から1~2
センチメートルぐらいの箇所を(たぶん弱く)切ってしまっ
たと思われる。
血はかなり出ただろう。生母はパニックに襲われただろ
う。数秒後 同居する姑のことも過ぎっただろう。
包丁が切ることで 爪を形成する組織を変えてしまい
以来 いわば「くの字型」の爪が 死ぬまで生えてくるこ
とになった。
「はじめての価値観が降りてきた」。
それは約六十年間行方不明(それどころか存命か否かす
らわからない)の生母が 我が息子の爪に書いた息子への
手紙だったのではないか! という価値観だが この価値
観は一体どこから降りてきたのか。
ノンフィクション ハラキン
闇から一転 舞台照明が歓声をあげるように点いて フィ
クションがはじまるように そのノンフィクションははじ
まった。なぜ そこに三歳のオレがいたのか いかなるもの
からも未だ説明はない。
布団が川の字に敷かれていて 祖母と父親が布団から起き
上がっていたように思う。いや実はよく覚えていない。玄関
先に(玄関などというものがあったのかどうかすらわからな
い)家出していた生母が 世話役(恋人?)の男といっしょ
に 家出の挨拶!に来ていた。という事の次第を 三歳のオ
レがこの現場で理解していたというのは どういうことか。
写真一葉のようなノンフィクションに 後からさまざまな
肉付けや種明かしが加わったのかもしれない。神々 妖怪
妖精などの仕業で。伝説が時系列を超えてふくらんでいくよ
うに。つまり当時の現場では オレはなにもわかっていない
ただの幼児だったのかもしれない。
このノンフィクションの起承転結 特に「結」がどうなっ
たのか まったく記憶が無い。「結」の絵具が経年劣化し、
あげく消えてしまったのか。
このあと生母はおよそ五年ほど行方をくらまし オレがた
しか小三のときに オレの前で復活した。
跳び箱の倉庫 ハラキン
男児が小学校の低学年(おそらく三年生だった)のときに
独り旅人のように現れた生母。家出して行方不明になってか
ら およそ五年ぶりに 放課後の小学校にやってきた。
「おとなの女の人があんたに会いに来てる」と クラスメー
トの女児に言われて 男児は 電流がからだを貫くように誰
かわかった。
放課後の陽は強い斜光で 跳び箱の薄暗い倉庫に現れた生
母は 一瞬逆光に荘厳されながら 我が子の名前を呼び捨て
て 「元気にしてたか」と泣きながら訊いた。
短いやりとり(男児の 生母に対する他人行儀な態度が
久しぶりの再会をも 短くしてしまったのかもしれない)の
後 「またここに来てもいいか」との生母の問い いや願い
に 男児は 首をタテにもヨコにも振らなかった。子役の演
技みたいになってしまったのは 生母を愛していなかったか
らだろう。もっと言うと 胎児から幼児に至る時節に 母親
の胎内でまどろみ 母に頬ずりされ 抱きしめられた と
いった触覚の肉体的記憶がなかったからだろう。
視覚でなく 聴覚でなく 味覚でもなく 嗅覚でもなく
母なるものは触覚だった。
演技の洞窟へ ハラキン
両手を前で組んで
腕組みをして
腕組みをほどき
また両手を前で組みなおす
突然声を張る
いったい十五年間も
政府はわが国をどこへ導いたのだ
何億とあった金は
すっかり無くなった
両手を顔の高さに上げ 振り下ろす
両手を顔の前で何度も振る
右腕を右横に上げ 手刀のように振り下ろし
引きつけ また振り下ろす
左掌を受けとし 右拳で叩く
メモを一瞥
右手で前方を指差し 右手を躍らせる
右腕を右横に上げ
幾度も人差指を突きつける
右手を舞踏のごとく動かす
メモを一瞥
腕組みに戻り
右腕と右手で
打撃の連打
数字の切れめごとに打撃 打撃 打撃
失業者は次々と増えた
百、二百、三百、四百、五百、六百、七百万
今日では七百万から八百万だ
小さな飛行機 笠原仙一
この冬一番の寒い朝がやって来ました
さあ 待ちに待った孫達との凍み渡りの日です
地蔵堂の三叉路の向こうは
誰も気にもとめないような田んぼの世界ですが
僕と孫達には
太陽の下に浮かびあがる日野山と
朝日に照らされる鬼ヶ岳
そして 側にはお父さんの勤める工場もあって
車を止めては眺める 美しい場所なのです
それが今日は澄んだ朝日に輝いて 一面真っ白
神聖な純白の世界へ足を踏み入れるかのように
おそるおそる 一歩一歩 歩き始めます
と 突然 孫達は嬉しそうに 腕をいっぱいに広げて
小さな飛行機になってクルクル クルクル
それはもう アクロバット飛行のように走り回ります
あらら あんなに遠くまで
お父さんの拍手が今にも聞こえて来そうです
未来達が 力いっぱい手を振っています
新しい時代 笠原仙一
今頃になってやっと 時代と科学は
深く人々の心の奧に潜んでいた愛の光の扉を開けたのです
心は次第に光に照らされて
理性と真理の中で
愛おしさと優しさに満ちた心で
己の有り様や世界を眺めたのです
すると驚いたことに世界の真実は 命に満ち
優しさに満ち 友に満ち 科学の法則に満ちていたのです
それは 五月の新緑のささやきのように
静かに光り輝き 力を放っていたのです
そして世界は その真実を生きる糧にして
新しいヒト属の生き方を模索し始めていたのです
そうです 新しい時代はすぐそこまで来ているのです
それなのに あぁそれなのに 日本の僕たちは一歩も前に進めず
いつまでも鎖と傲慢強欲に縛られて
滅びの予感と 流れのままに 口をつぐんでいるだけなのです
腹と背中 吉田定一
お前と俺は 表裏一体の間柄なのに
これまで言葉を交わしたこともなかったな
だって おまえさんは
何時だって 背を向けているではないか
ビール腹の兄さん―― あなたも世間から
腹黒いオッサンと言われているよ
同じ身ではあるが 背中と大事な腹を
一緒にされては 腹が立つ
自身を守るためには
多少の悪口を言われたって致し方ないさ
背に腹は代えられない
控えめに 団栗(どんぐり)の背比べ?! と言ってくれないか
遠く火事、背中の灸(きゅう)だ…
済まないが この辺で退散するよ
だが悲しいかな 表裏一体の間柄
逃げるに 逃げられない
(ああ 背中の刺青(タトゥー)が泣いている)
寂しい表情を見せるなよ……
さあ これからお互い 腹を割って暮らしていこう
*遠くの火事、背中の灸 遠くの火事より自分に関係する小事の方が
気にかかるというたとえ。
ウミガメ 根本昌幸
ウミガメの産卵を見たことがある。
テレビで。
ウミガメはその時
涙を流すのだよ。
どうしてなのか
考えたことがある。
人間も涙を流すという。
ほかの生き物はどうなのだろう。
自分は涙には弱いから
じっとしてはおれなくなる。
腹の底の方から
なぜかしら
レジスタンスのようなものが湧き上がってくる。
なにに向かってなのだろう。
それはエールなのか
または別なものなのか
よくは分からない。
今でも時々
あのテレビの画面を思い出す。
光る涙。
一生懸命産む姿。
そこへ砂を掛けて
波間に帰っていく姿。
誰もいなくなると
人間はその卵を持っていく。
黙って。
これが人間です。
人間のやることです。
地に堕ちてしまった。
人間の本当の姿なのです。
わたしの胴体はどこへ 牛田丑之助
わたしの胴体はどこだ
足は 腕は
脳味噌のない頭蓋だけが大人しく他人と棚に整列して
隣人は頭が軽いとひそひそ愚痴るだけだ
洞窟の中は空気さえ微動もせず
それでも頭蓋を離れられないわたしたちの霊魂で
あの世との境界領域は大混雑だ
もしも肉体あるものがここに入ってきたなら
歪んだ時空圧で記憶を喪なうだろう
こうして多種多量生産で肉体が腐乱し
やがて骨になり頭蓋は頭蓋、胴体は胴体と
まとめて整頓されるのがすなわち風葬だ
わたしが死ぬ時に胸に疼いていた
気がかりも哀惜も妄念も
それどころか執着もとっくにどこかへ消えてしまった
死んだら霊魂は羽虫になって自宅を訪れるというが
わたしがなれるのはせいぜい土浅く潜る蚯蚓だろう
足よ 腕よ 胴体よ
ほかの連中と仲良くやっているか
縄で縛られまとめて積み上げられ
もう自分が自分とはわからないかも知れないが
お前たちと野を駆け交合した遠い日々を忘れてはいない
こうしてわたしは
ウィスキー樽のように整列した頭蓋として
分厚い椀状の骨が風化するまでこの地で並び続ける
あの世との境界領域を右往左往する霊魂とともに
十把一絡げの白々とした骨たちとともに
一両編成 牛田丑之助
老いた用務員もいなくなった廃校のように
発車のベルがホームで虚ろに鳴り響き
一両編成の列車が出発し
あてどなく水の上を紅い草原を滑っていく
乗り合わせた輪郭のない客はみな
無言で俯いたきり一度も窓も私も見ないが
それはなぜなら彼らは私自身だからだ
時々踏切を通り越しドップラー現象で
電鈴が三度低い音階を鳴らし
遠ざかりながらいつまでも耳奥で響き続ける
そこにも輪郭のない買い物客や蒼い犬や行路徘徊者が
いつ開くかも分からない遮断桿の前で
何ものも見ずに立っていて
彼らももしかすると私自身なのだろうか
あるいは私自身が彼らなのかもしれないが
この列車はいつどこに着くのか
決してどこにも着かないのか
同行者が時々声にならない不安を訴えても
何の効果もない
誰も救済してくれず 誰のことも救済しない
だからこうして行儀よく膝をそろえて
臙脂色の客席で硬いコイルを尻に感じながら
座り続けるしかないのだ
たとえ私自身の輪郭が薄れていったとしても
気づくと私はベッドの上にいた 牛田丑之助
気づくと私は硬いベッドの上にいた
そこは多くの消しゴムのベッドが並べられた
まるで野戦病院のように思えた
たくさんのベッドがありながら 寝ているのは私一人のようだったが
いつの間にか隣のベッドの上には鳥かごがあり
中には十三色に輝く孔雀がいた
しかし起き上がってもう一回見ると今度は深い海のように蒼い犬であり
犬は私を見て吠えもせずに涙を流すのだった
私にはわかっていた 犬の泣く理由が
私が羨ましいからだ
羨望の涙は私の中のよきものを そして真を善を破壊し否定する
だから泣くのはやめてくれ と言いたいのだが
口の中にはいつの間に綿が詰め込まれていて
私は辛うじて息をしながら何とか泣くのをやめさせようとする
しかしすべては徒労だ
私はあらゆる希望を捨て羨望と悪意の土砂降りの中で
ベッドでもう一度横になる
そしてすぐに覚醒してしまう浅い眠りにつく
一方で起きた時に蒼い犬が姿を消しているのは分かっていて
それはどこか懐かしい何も見えない景色だ
前夜 牛田丑之助
トイレに飾られた黄色い花が 枯れながらにして咲いている
明日家族全員が断頭台に登る王室一家の最後の晩餐
姉は妹の面倒を見
母は慈しんだまなざしを送り
父は上機嫌に赤葡萄酒を傾け
楽団はショパンの室内楽を奏し
料理人は銀の皿を運んでくる
静謐で穏やかで麗しい時間だ
なぜ滅亡の直前はかくも月光のように輝くのだろう
なぜ終焉の囁きはかくも微風のように耳元を吹くのだろう
なぜ枯れながらにして咲く花はかくも美しいのだろう
禁断の果実を食したあとは
死神があの世へ連れ出すように
一人また一人と食卓から消えて
やがてビロード張りの椅子には聖痕のように影だけが残る
そして影は一晩中 静かに一族の歴史を語り合う
民衆は残酷さを愛し 自らには寛容さを求める
黄色い花はその時になっても眉ひとつ動かさず
口元に笑みを浮かべ優雅にスカートの裾を翻し
十三段の階段を踏んで断頭台に首を差し出すだろう
その時 世界からひとつの神話が消滅する
傘 来羅ゆら
激しい雨音が
私を閉じ込めるから
傘に
穴をあける
突く
切り刻む
ナイフで
空を見上げる
昏いかなた
大きく開いた目に
雨 は
撃つ
雨が届く
私に
容赦なさに奪われる
痛みの清しさ
残骸から
聞こえる
遠く深く
耳もとに
傘の骨の声
人生病 吉田義昭
僕の人生を訪ねて来て
「生きよ」と告げる人がいる
いや 僕は生きています
こんなにも深く
心貧しい人生を楽しみ
妻が死んだ後も
ほんの少し慈しみ
寂しい人生を楽しんでいます
僕の人生を笑いながら
「生きよ」と告げる人もいる
いや これが僕の生活
名づけようのない一日の後に
不確かな一日が続き
誠実に生きて日が暮れて
涙を流せず
悲しい人生を楽しんでいます
僕が人生を作れないのは
人生論を語り過ぎたからです
とにかく僕は生きていて
ただ単調な日々を繰り返しても
僕の人生に僕がいないと
そう気づけなかったのですが
不必要な時間を削ぎ落しても
透けてしまった僕の人生が見えます
僕の人生は僕の友人のふりをして
何処で生きていたのでしょう
いや 何が何でも僕の身体の中に
僕の人生が生きていると信じます
何かが欠けてしまっても
紙よりも薄っぺらな人生でも
「もっと強く生きよ」と
私の声が耳に響いて聞こえます
渡り鳥から人間さんへ 阪南太郎
私たちは渡り鳥
季節が変わるたびに
世界中の空を旅するの
私たちには国境なんてないの
うれしいのは
行く先々で人間さんが色々な言葉で
「ようこそ」
と言ってくれること
大きな島の「ようこそ」も
小さな島の「ようこそ」も
私たちを元気に羽ばたかせるの
私たちは信じているの
人間さんには
「大好き」
の言い方も
「ありがとう」
の言い方も幾千通りあるのよね
歌う理由 加納由将
今歌っているんだ
あんなに自分の体を
硬直させていた
大音量の前に立って
歌っているんだ
あなたに届けたい
気持ちがあるから
歌えるようになったよ
あなたに届けたいから
まだ
練習しないと
あなたが飲み込みやすいように
体に広がっていくように
今日も歌っているよ
誰かが聞いていたら恥ずかしいけど
スピーカーから聞こえる大嫌いな自分の声を聴いている
仏法真理 中島(あたるしま)省吾
私の過去の人生の後半は苦しんで地獄だった
今の自己中な社会の時の中で精神病で苦しんだ
最悪だった
一人ぼっちでお母さんも死んだあとも
三十代後半男野郎一人では
泣きっつらに蜂だった
誰一人助けてくれなかった
僕は今、逃れた心地よい山中の家にいる
死後にいる
逃れたように
誰も追って来ない小鳥が鳴く晴れた山中の家
男青年部たちが交差に
(○○○をしている)
自分の相手は? というと誰も決まらず
男青年部たちが扉を開けて何処かへ行った
急に
かわいい顔した過去の
ジャニーズジュニアの時代にレッスン所で私が惚れていた
同性幼年なのに緊張するぐらい惚れた男の子
あのかわいい顔だが、羽のついた男の子が
入ってきて
私の服を脱がして、イケメンマスクを脱がして
外の洗濯機の前で洗濯
私の服とイケメンマスクはすっかり汚れていた
天使のような? 厳しい機械的なような? 男の子は一生懸命洗濯していた
次の世は
地獄界か畜生界・動物界だと知った
お疲れ様でした
着てた私の服と私のイケメンマスクは
次の使用者に渡す
いつの間にか服もイケメンマスクも全部返してて
次に
宇宙世界の生命のある星のどこかで
私のイケメンマスクで
実験する人に渡す
なんの山中の家かわからなかった
思春期時代観たあのかわいい
ホモじゃないのにもんもんとさせたあの男の子が
鬼のような、天使のような、あっさりと機械的な使いのような
僕はあのかわいい男の子を再び時空を超えて口説こうと想った時
急に男の子がなんかのボタンを機械的に押した
僕が消えて
こんにちわ
晴れた陽気に
ダンゴムシさんかアリさんとして
ごそごそと僕は今いるんだ
好きなメスのダンゴムシさんかアリさんの
後ろを追いかけて
晴れた陽気ににっこり
食べ物を探す
平和だった
畜生界はあのかわいい顔の男の子からのプレゼントだと知った
扉を開けて何処かへ行った男青年部たちは
地上に出てこれない下の界、○獄界だったのか?
やっぱり、あの男の子でも
ジャニーズジュニア時代に
もんもんが行動にできたマスクの僕だった、服を持っていた
あの男の子もいざ推されて、口説かれてたら僕が好きだった
僕だけ○獄界よりも
上の畜生界に行かせた
愛が来る、愛の象徴のような、前の自分のマスクと服だった
生を受けて 中島(あたるしま)省吾
生を受けて
こっちを向いている野生の鳩
食べ物をねだる
集団で飛び回る雀
仲間はずれの雀
動物も人間も苦労している
人間の日本では
東京オリンピックが中止か無観客になるらしい
みんな苦労している
みんな生きている
みんな一緒の仲間さ
ぼくはなぜひとりかというと
ぼくも、なかまはずれに「わかい、ぼくしせんせい」にさせられたなかまさ
仲間さ
生を受けて
その「ステージ4」にて 下前幸一
喧騒をはぐれて
奇妙な静けさにいる
二〇二一年冬、第三波
一月六日
新型コロナ感染、六〇〇一人
死者、六五人
爆発的感染拡大
一月七日
新型コロナ感染、七五七〇人
死者、六四人
緊急事態宣言発令
不可触の洪水に呑まれて
高止まる現在
鳴り渡る警報にも驚きは薄れて
報道は数値を重ねていた
新規感染者と、死と重病者と
あるいは病床逼迫
重症病棟の日々
人工呼吸器と
人工肺エクモの静かさに
君は確かだろうか
思いもよらなかった場所に
僕たちはそれぞれが閉ざされて
足が届かない現実に浮かぶ
ホテル隔離の冷えた弁当と
自宅療養の不安と
収容によく似た暮らし
不確かさの舳先に
不安な身を乗り出しても
見えるのは白い霧ばかりだ
普段着の日常がささくれる
何気ない言葉の刃が
夜更けの明かりに突き刺さる
君は確かだろうか
一月七日
世界の新規感染者、一一六万人
死者、二万人
国境は閉ざされていた
しかし僕たちは我知らず結び合い
お互いの触角を手探っていた
一月七日、新規感染者
南アフリカ、二〇九九九人
ポルトガル、九九二七人
アルゼンチン、一三八三五人
イギリス、五二六一八人
イラン、六三六〇人
ウクライナ、九三二〇人
イスラエル、七六〇〇人
エジプト、一二一九人
レバノン、四七七四人
タイ、二〇五人
……
北朝鮮、不明
国益は虚妄
高病原性鳥インフルエンザ続発
一月十一日、千葉県の養鶏場で確認
一一四万五千羽を殺処分
感染症はメッセージ
それは告げる者
言葉よりも強く僕たちをうながし
あるいは手招きする
人気ない路地の
ほの青い希望の揺らめきに
さあ帆を上げよう
<PHOTO POEM>昔日 長谷部圭子
娘と戯れた石の海
今 一人 歩く
行く手を阻む砂利
今 一人 超えてゆく
小石を砕く ピンヒール
今 響くのは 一人の足音
どこへいくの
風がきいた
会いにいくの
あの日の面影に
<PHOTO POEM>僕の相棒 中島(あたるしま)省吾
おう、出っ歯の黄色いおっちゃんです
私もアラフォー
若返りの出直しはない
詩って難しい
とか、悩んでいる
詩の採用にも苦労するんだぜえ
おい、僕はオカメインコの名無しです
ご主人様は
一日中横になって
暇で苦しんでいるよ
僕は飛びたいけど
出っ歯の黄色いおっちゃんの子守のように
一緒に暮らしています
おんなじ空気吸っていますが
時々換気してほしいだ
僕は暇じゃないよ
食事が好きです
なんか人間が喋ってるの
覚えたいので
ご主人様がなんか電話で言ってるとき
僕も言葉がわからない言葉を出します
マリアンヌ ―歌のために 左子真由美
むかしパリの街の片隅に マリアンヌという娘がいた
愛の風船を売る娘 涙をやさしさに変えて
・・・・・・・・・・・・
風船売りのマリアンヌ
街に通りに公園に
どこにでもでかけて行く
風船売りのマリアンヌ
その前にはいろんな仕事をした
でも何も続かなかった
風船をもったら
誰でも幸せになるわ
たとえ少しの間でもね
風船売りのマリアンヌ
ツンと突き出した胸
ゆれる亜麻色の髪
カフェで語ったマリアンヌ
人生はたやすくない
でも だから面白い
風船売りのマリアンヌ
昨日男と別れて
屋根裏部屋を飛び出した
ポケットにはわずかなコイン
寂しいときはオレンジをかじる
陽気で考えなしのおてんば娘
風船売りのマリアンヌ
でもとびっきり人がいい
いつも夢の風船を売っている
もしいつか街角で
マリアンヌを見かけたら
忘れずに声をかけて
・・・・・・・・・・
むかしパリの街の片隅に マリアンヌという娘がいた
愛の風船を売る娘 涙をやさしさに変えて
待つ 中西 衛
街の夕暮れ
神社の石垣に座って
診療所がえりの家族を待つ
通勤帰りのサラリーマンや
買い物帰りの女の人たちが
自宅へと急ぐ
家族のにぎやかな
団らんが待ち受けているのだろう
秋の夕暮れは陽の落ちるのが早い
ほうけたように待っている
円錐状の神社の欅の大木は
上から下へ
黄 薄緑 暗濃色と多彩な影となって
入り混じり
入日をからだいっぱいに受けながら
沈んでいく
ときのまを
繰り返し春をみごもる
裸木
まぶしかった見事な秋
ひとびとを慰め過ぎ去った
鳥たちや虫たちの動き
日頃忘れられた気弱な魂たち
せわしかった季節の移り変わり
揺れた
老人の心中は穏やか
ここには勝者も敗者もない
アスリート 卓球 中西 衛
闘うのである
2.74メートルの卓球台をはさんで
直径4.4センチの白球が
100キロのスピードで行き来する
顔をしかめる眼や口のうごき
相手の一挙手一投足
睨みつけるまなこ
はじまるサーブ
次の一手に全神経が集中される
緩い球 チキータ 逆回転
身構え激しく打ち返す
頭脳と体験が反射するのみ
多種多様に変化する球を打つには
無心に持っていくための
精密な思考が求められる
難しいはずのボールの回転
見えないはずの回転を見極め打つ
相手の球をうけ反撃する素早さ
どこからか
火薬のにおいがする
男性には男性の力強さがあり
女性には女性のしなやかさがある
この激しいスポーツに
使われている白球はあまりに
か弱かすぎないか
その一瞬一瞬に人は感動し
ほっとする
真っ正直にすわってみる 山本なおこ
真っ正直にすわってみる
遠くふるさとの一本の樹になってみる
せせらぎの小川になってみる
庭の日蔭にひっそりと咲いている
茗荷(みょうが)の花になってみる
真っ正直にすわってみる
銀行員だった村の幼馴染みの友の顔が浮かぶ
自殺したという
年老いた義母(はは)ひとり残して
奥さんが子どもを連れて村を出ていった
真っ正直にすわってみる
今日の今まで
ありのままの私であったのだろうか
原郷(うぶすな)が幻郷のようにして
ふるさとが私を叱咤する
真っ正直にすわってみる
私の胸に音もなく
さりさりと雪が降る
何かに祈りたいような
つつましやかな気持ちになってくる
光 水崎野里子
光を求めた
光は 逃げて行った
闇を求めた
闇は 逃げて行った
出口を求めた
出口は 逃げて行った
窓を求めた
窓は 逃げて行った
希望を求めた
希望は 逃げて行った
花を求めた
花は 逃げて行った
なんでも逃げて行く
でも しあわせだ
求めた ということが
求め続けたと いうことが
私の人生なのだ きっと
だから しあわせだ
笑いを 求めた
涙を 求めた
いつまでも 私は
求め続ける――そのしあわせ
歌を歌いたい 水崎野里子
歌を歌いたい
なぜか 今日
何でもいいから
歌いたい
道端に咲いていた
白い水仙 早咲きの
寒い風に揺られていた
寒くはないの?
いつか見た
真っ赤なひなげし
こんにちは
私の心も 赤いのよ
どこかで見た 裏町
どこかで見た 走る列車
遠い 記憶の 街
遠い 記憶の 森
雛祭り 父も母もいた
鯉のぼり 空高く
翻っていた 洗濯物
干されていた 布団
乙女椿
桃の木
クルミの木
遠い 秘密の 庭
あなたの微笑み
あなたの 涙
誰かが どこかで 哄笑する
しかめづらをする
歌が歌いたい
世界は 暗黒なのに
世界は 沈黙なのに
なぜか
今日 歌を歌いたい
あなたと
私が旅立つ時
おそらくは思い出す
両手に一杯の
野原の 花を