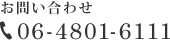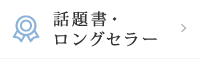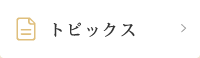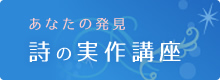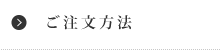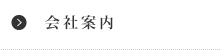![]()
161号 祭り
161号 祭り
- 秋 魚本藤子
- 森の中ですきとおる 野呂 昶(のろ さかん)
- かぼちゃ 野呂 昶(のろ さかん)
- 五月のブランコ 高丸もと子
- ポッ 高丸もと子
- 野いばらのオルゴール 高丸もと子
- アガメムノン 大瀧 満
- 輪廻 藤谷恵一郎
- 音楽 佐古祐二
- 1人で遊ぶ少女 葉陶紅子
- 夜(よ)には九夜(ここのよ) 葉陶紅子
- 朝になったら 根本昌幸
- 風鈴 清沢桂太郎
- スーパームーン 宇宙の詩 蔭山辰子
- わらいごと 神田好能
- 足の指 吉田定一
- 安さん金さん二人芝居 丸山 榮
- ぐったり 晴 静
- なぜ音楽 ハラキン
- 絡まった糸 加納由将
- 増殖 瑞木よう
- クリスマス讃美歌 中島(あたるしま)省吾
- 窓を開ける 水崎野里子
- 風 水崎野里子
- パリの空の下 ―― Sous le Ciel de Paris 水崎野里子
- 鴉(からす) 山本なおこ
- 父と子 中西 衛
- 〈シリーズ・手〉 暮れ方 原 和子
- 終ったもの 原 和子
- 現実/伺い/大雪 牛島富美二
- 恩寵 牛島富美二
- 春夏秋冬―2015 きだりえこ
- 一本橋渡れ 斗沢テルオ
- 陽のまだら 秋野光子
秋 魚本藤子
遠いところから
りんごが段ボールの箱にいっぱい届いた
両手に余る大きなりんごが
どっさり入っている
それを二つに切ると平面が見えてくる
その静かな平面を四等分
それをまた小口切り
もう丸い形は見えなくなって
何がりんごだったのか
わからないまま食べる
それでもりんごはなくならない
傷んではいけないので冷蔵庫に入れた
冷暗所に保存と書いてあるので
部屋の隅の暗がりに隠した
古い日記帳のように
箪笥の引き出しに入れて忘れた
籠に入れて棚の上に置き
静物画にした
元の木から遠く離れて
りんごは
テーブルの上 テーブルの下
家のあちらこちらに
秘密のようにころがっている
歩く度 りんごの形にぶつかる
その丸い影を踏みそうになる
家はりんごを孕んで
柔らかく膨らんでくる
秋も深まったある日
りんごが届いた
何がりんごなのかわからないまま
家はうっとりと傾いていく
森の中ですきとおる 野呂 昶(のろ さかん)
白樺の並木の金のきらめきのなか
風が渡っていく
あなたとわたしの よろこびが
輝きながら 木々の梢に降りかかる
あなたが先をかけ
わたしがうしろを追いかける
わたしが先をかけ
あなたがうしろを追いかける
なにがおかしいのか
あなたが笑う 笑う
わたしも笑う
足元で光の金が ほのおをあげ
笑い声が 森の緑の中ですきとおる
かぼちゃ 野呂 昶(のろ さかん)
どっしりと力強く
大地に腰をすえ
木々や小鳥たちの
語らいに耳をすませ
すんだまなざしで
周囲を見つめ
内実を高め
ふとらせ
今
畑のかたすみで
ごろんと寝ころんで
空を見ている
五月のブランコ 高丸もと子
じゅんばんよ
つぎ こうたいね
いーち にーい さーん しい・・
空にも
きこえる大きな声で
振り子が揺れる分だけ
時が過ぎていき
一緒に数えていた友達も
いつの間にかいなくなって
ブランコの音の消える辺りから
かすかに人の近づいてくる気配がする
わたしの後ろの方で見え隠れしながら
陽気にはしゃいでいる気配がする
まだこの世に生を受けていない人々が
わたしの降りるのを待って
すでに列を作り始めているらしい
まわりが年ごとに眩しく
美しく揺れて見えるのは
限られた時の中でしか漕げない
と気づき出したから
目を閉じる
今 若葉が萌えだしたばかり
地球の丸みにそって
ブランコの揺れるのが見える
ポッ 高丸もと子
「あなたがいないと
わたしが さびしい」
だなんて 誰
こんな額を買ってきて
わたしの机の上に置いたのは
すきだとか
あいだとか
あまり口に出さない人が
思い出したように
ポッと
今日ジャスミンの花が咲いた
それも
ポッと いい始めの言葉のように
小さい白が三つ
野いばらのオルゴール 高丸もと子
立ち止まって
たぐり寄せている
この不思議な気持ちは
どこから?
野いばらの棘に
風が触れて
まわる
まわる
野いばらのオルゴール
遠い年月から
降り立った人のような
なつかしい風よ
棘をはじく痛み
棘を持つ痛み
傷つけあった遠い日を
今日のように奏でるためだったとは
微かに鳴るオルゴールが
まぶしい
アガメムノン 大瀧 満
春雷のように
遠く去っていった君よ
いつも君はひとりで
ギリシャ悲劇を演じていたが
はるか紀元前の空に向かって
おおらかな叫びを放ってはいたが
その過去をきっぱりすてて
ふるい文化のかおる西の果てを
君はゆうぜんとさまよっているそうな
そして ストイックな君は
きびしい自由と孤独を背負い
うつし世を明るく否定しながら
はるか紀元前の森の中へ
大股で歩いて行っただろう
ああ あれから半世紀
アガメムノンよ
もう現代になどかえってくるな
*アガメムノン ギリシャ悲劇三大作家の一人、アイスキュロス作
『オレスティア』(三部作)の一篇にでてくる有名な武将。
輪廻 藤谷恵一郎
輪廻の海の混沌に
沈みゆく我という泥舟
欲望の櫂
輪廻の海の青さに
どんな矛にも貫かれそうな盾として掲げる
白い帆
葦の汎舟
寒風吹き止まぬ
輪廻の宙の冥さを
領巾のようにまで裂け 垢汚れた襤褸のみ
身に残し
巡り続ける
自縛の業の魂
音楽 佐古祐二
ささやかな日常に
誰かが言ったちょっとした言葉に
本や映画の中の台詞に
空や
海や
犬や
猫や
草木や
夕焼けに
音楽がある
音が出る一歩手前の沈黙のなかに
音を出す一歩手前の息遣いのなかに
音楽がある
声もなく
溢れるなみだに
音楽がある
塗りつぶされた黒い画面のなかを
くちびるから
空間に
か
す
か
に
流れ出す
白い粒子のような
かなしく色っぽい
最弱音(ピアニッシモ)の音に
音楽がある
1人で遊ぶ少女 葉陶紅子
1日を 1人言いい遊ぶ少女(こ)は
ベッドの端に 1人で眠る
仲よしの いつも2人で遊ぶ少女(こ)と
1つベッドで 2人で眠る
1日を 部屋にこもって遊ぶ少女(こ)は
1人言いい 1人で遊ぶ
1日を 部屋で2人で遊ぶ少女(こ)と
おしゃべりしても 2人で1人
遠くまで 1人言いい歩く少女(こ)は
見知らぬ町で 途方に暮れる
手をつなぎ おしゃべり散歩るんるんの
見知らぬ町で 2人で迷子
天使らの翅音を聞いて 遊ぶ少女(こ)は
1人で2人 永遠(とわ)を微笑む
夜(よ)には九夜(ここのよ) 葉陶紅子
青き夜 果芯の種子を思念する
肌に浮く汗 微かに匂う
眸(め)を閉じず 蜉蝣(かげろう)のごとただよえば
夜(よ)には九夜(ここのよ) 日には十日を
透かし見る 肌(はだえ)のうちを走る血に
ひと日のいのち いだきて生きん
九夜(ここのよ)も十日も生きる 蜉蝣(かげろう)と
思えば安し われがいのちよ
わが乳房(ちち)に顔をうずめて さかりする
かのこ愛しき ひとりの宵は
この肉に残せし指紋 あかしとて
匂える汗の なかに綴じませ
わが乳房(ちち)よわれが下腹よ 青き夜に
匂える汗の ままに消え逝け
朝になったら 根本昌幸
昨夜 私は何を書こうとしたのだったのだろう。
夢の中で。
朝になったら
もうすっかり忘れてしまって
思い出せない。
そうだろうとも
血圧の薬は飲む。
安定剤も飲む。
サプリメントも飲む。
アルコールも飲む。
これで寝てしまうんだから。
思い出す
などというのがおかしい。
机の前に座って
ニヤニヤしていると
犬が寄ってきて
不思議そうに
私を見ている。
ココ
どうした?
おじいさんは頭が
変になったのかもしれないんだよ。
けれど
まだ大丈夫。
何かが書けるうちは。
しかし 気になることが
一つある。
古里はどうなっているのか。
風鈴 清沢桂太郎
春には 春の音を響かせ
夏には 夏の音を響かせ
秋には 秋の音を響かせ
冬には 冬の音を響かせ
風を選ばず 東西南北の風に
風鈴は 鳴る
大空の中
ただ一等に般若を談じて
鳴る
りん りーん りん
りん りーん りん
りん
スーパームーン 宇宙の詩 蔭山辰子
行基大橋を南へ
右手直角 大和川河口から難波津へ
今日の別れを惜しむかのよう
驚くばかりの赤い夕陽
間もなく左折 十二号線へ〈*1〉
大阪平野を抱く東の山並み
さっき見た夕陽がここにもと見紛う赤い満月
これは昇ったばかりの スーパームーン
今日を明日へと懸橋のステージ
「菜の花や月は東に日は西に」
と詠んだ 旧古(いにしえ)の俳人も〈*2〉
この日 この月を感嘆したのだろう
初めて目にした宇宙の営み
時間を忘れたひとときの陶酔境
Cosmos Poem
*1 堺大和高田線
*2 与謝蕪村
平成27年9月27日 記
わらいごと 神田好能
うふふ
うん 何も出来なくなったら
おしまいね
うふふ
そんな言葉が出るようになったら
おしまいね
うふふ
おしまいねと言える
そんなら まだまだ
おしまい じゃあない
うふふ
そうか そうね
おしまいねと
自分に言えるうちは
まだ まだ
おしまいではない
そんな想いを口に出して
自分をわらう
そんな想いが
あるうちはまだいいかな
そんなことを他人に
言ってみる
そんな時間がある
わらいごと
ではないのに
わたしは笑っている
そして自分を
ごまかして
何とか今日も
一日すむことを
祈っている
九十歳の
女である
足の指 吉田定一
つとに このごろ
足首が冷え 痺れたまゝだ
老いは足から 病は気からと
良く言ったものだ
寒空で冷え込んだ ちっちゃな足を
母は柔らかな股にはさみ入れて 暖めてくれた
ああ あの時の暖かさが 優しさとなり
いつしか 慈しむこころとなり
いま愛おしさとなって 涙する
そして良き人の 愛の架橋となっている
暖かいあの感触が こころの来歴となって
遠く近く 記憶の岸辺を洗う
そして いまなお
余計な想いをさせないようにと
痺れて冷やっこくなった老いの足指を
暖め 気遣っている
安さん金さん二人芝居 丸山 榮
安さんは 三代目の次男坊 金さんも三代目も三男坊
長男次男を押しのけて 主役をはっていらっしゃる
目をかけてくれた じいさまとうさまに 報わねばならないと
なにやらよからぬ企てをしているようで
権力握った二人には 判断 決断 我が儘いっぱい
そのうえ怒りが爆発すれば 首がいくつあっても たりやせん
安さんは 憲法かえたい一心で 憲法違反の法律を 次々作って高笑い
目・耳・口をふさぐ悪法できれば 金さんの国に似てくるよ
金さんの無駄づかいは ミサイル飛ばせば 国民ニコニコ バンザイで
約束守らず 気にくわないと どんどん処刑だもんね
安さんだって 日本国憲法が気にくわないと 目・耳・口をふうじようと
どんどん 法律 代えてしまうし もう金さん状態よ
安さんの 無駄づかいは 何といっても大名旅行
次々にお金を ばらまいてくるけれど 自国の子供の貧困は 増すばかり
高校 大学入学費用をただにすれば 若者の未来が明るくなるのに
日本国憲法は よろずの神の中心にいて 平和を愛し 人々を愛し
日本国憲法は 世界の神をつなぐもの 平和を祈り 国々を敬いて
ぐったり 晴 静
青い空 白い雲 赤い陽
ゆら ゆら ゆら
白地のマストが小波に映る
雷鳴とどろき瞬時に荒波
ゆら ゆら ゆら
白地のマストが小波に映る
銀の鱗を輝かせ
命の限りに跳ねていた
小魚一匹
なにやらぐったり
漁師ひとり
漁具の手入れ
命の限りに跳ねていた
小魚一匹
ひと際ひと跳ね
微かにぴくっ
とうとうぐったり
漁師の横に
くわえ煙草は皺深し
青い空 白い雲 赤い陽
なぜ音楽 ハラキン
1
なぜ音楽というものが生まれたのか
音楽でなければならなかったのか
その個人において
人類において
文明のセンチメンタルにおいて
意識がこしらえた闇に
ひとりいる
闇でもなお、顔に原色のペイント
観念が
架空の太鼓を叩かざるを得ない
右手のひらで叩く
一音
観念を黙らせるために
(一音でやめればいいものを)
ふたたび右手のひらで叩き
すぐに左手のひらで叩く
二音
右と左で音が違ってしまう
闇じゅうから
たちまち意識が群がってくる
ああ
ついに音楽
闇に、頬をなでる俗物がそよぎ
役所の拡声器から
西欧古典音楽が飛びだす
なぜ観念を黙らせたのか
なぜ音楽というものが生まれたのか
音楽でなければならなかったのか
2
なぜ音楽というものが生まれたのか
音楽でなければならなかったのか
感覚器官が燃えるから
舞踊と歌と器楽演奏と見世物を
修行僧が
観たり聴いたりすることを
聖者は禁じていた
聖者が死んだら
その門下には
音楽があふれた
酒を飲みながら
ジャズの生演奏を聴いていた
俺の隣りに
古代のナーガールジュナ先生が
坐っていた
いま忽然とあらわれたかのように
古代から坐っていたかのように
先生は瞑目し
サックスは咆哮する
「怒りの毒が強い
娑婆世界に抗議しているのか
見よ
奏者も聴衆も
感覚器官が燃えさかっている」
先生は俺にささやいて
掻き消えた
帰路
星のかなたから聞こえた!
音楽を禁じた聖者以前からあるという
天の音か
なぜ音楽というものが生まれたのか
どうしても君は音楽が欲しいのか
3
ウラの世界からは音楽が聞こえてこない。俺をウラがえすと、ウラの俺があらわれてオモテの俺に問いかけてきた。オモテの補色というわけでなく、モノトーンでもなく、ウラの色彩というほかない顔色で「オモテでは、なぜ音楽というものが生まれたのか。音楽でなければならなかったのか」。オモテの俺は答えた。「生きることそのものがほぼ音楽だから」。ウラが反論した。「ウラだって生きているが、音楽はない」。
祭典はあるが音楽はない。大行進は靴音だけ。舞踊はあるが音楽はない。オペラはない。恋はない。紀元前にオモテの聖者が神通力でウラを訪れ、音楽がないことを褒めたという。ウラの俺は続ける。「オモテの人間は、心が弱いから音楽を生んでしまった」。
さらにウラには叙事はあるが叙情はない。これをはかなんだオモテの神々(天に住む、人間よりもランクが上の生きものたち)は、ウラの生きものたちをオモテに変換し、いままさにウラの世界を閉じようとしていた。ウラがなくなっても、この問いかけだけは化石のようにオモテに伝わるのだろう。
「オモテでは、なぜ音楽というものが生まれたのか。音楽でなければならなかったのか」。
4
なぜ音楽というものが生まれたのか
音だけではだめだったのか
なぜ土というものが生まれたのか
水だけではだめだったのか
なぜ水というものが生まれたのか
火だけではだめだったのか
なぜ火というものが生まれたのか
焼かなければだめだったのか
なぜ風というものが生まれたのか
無風だけではだめだったのか
なぜ花というものが生まれたのか
咲かなければだめだったのか
なぜ恋というものが生まれたのか
愛だけではだめだったのか
なぜ戦争というものが生まれたのか
平和だけではだめだったのか
なぜ憎しみというものが生まれたのか
慈しみだけではだめだったのか
なぜ空性というものが生まれたのか
永遠の実体だけではだめだったのか
なぜ歌というものが生まれたのか
歌わなければだめだったのか
なぜ音楽というものが生まれたのか
音楽でなければならなかったのか
絡まった糸 加納由将
僕は
疲れたのかもしれない
遠い日に
あなたが
投げ込んだ
僕の体内に
掘り込んだ
夢は
もつれた
糸
いまだ
絡まったまま
僕は
息苦しくなった
今も
成長する
欲望は
時に縛り上げ
苦しめた
糸さえ飲み込み
消化してしまったそうだ
増殖 瑞木よう
目の奥から
苦味が降りてくる
白くけぶる 視界
白く濁る 空
音が聞こえる
世界は音で満ち
耳鳴りとともに
響いて増殖する
苦行とも思える時間
過ぎ去るものか
とどまるものか
見えない景色
増えていく音の
向こう側
クリスマス讃美歌 中島(あたるしま)省吾
クリスマスには讃美歌を、とは思っていたけど
被災地の人の涙と想えばできない
ネットでとある政治参加の宗教信者が
人権も覆されて代表先生とかを
何も知らないネットの若人が罵倒しているのを観て
誰がそんな宗教入るかとネットの書き込みの素人の評論
でも正反対にキリスト教は優秀とか書き込んでるのを観て
でもその罵倒されまくった宗教の
新聞を毎朝、無冠の友として
クリスマスイブもクリスマスの
寒い雪の真夜中でもおばちゃん一人で
息もはー
息が白く くもって喘息なのか
息もぜえぜえして
でもクリスマスでも
キリスト教とは違うその宗教の信者の方に配達している
深夜3時に私の住む団地のエレベーターで
ドッキングして談笑した去年
「無冠の友と言われて給料ないんです」
でも、ネットで非難されている
その宗教の会員さん待ってるからと笑顔で
寒い雪の真夜中に自転車で
近所の会員さんの家に配ってるところを去年観た
福島県でも生きようか必死で年末だとか迎えて
必死で戦ってクリスマスどころではない
自分がキリスト教は正しいと言っているネットアンチと一緒になって
クリスマスがいい、讃美歌なんて書けないから
一緒に泣いたりとか、笑顔とかみんな言ってるけど
心は折られてる 創り笑顔を見せろとみんな芸能人は慰問しているけど
津波で家族も財産も失った
福島県がんばれと評論家はテレビで軽く言う
そんな中でみんな頑張れとか励ます
心は完全に折られている
✝優しいあいの詩✝
失ったものは帰ってこない
団体の敵は味方にはならない
助けてくれない
刹那無常の人生の生き方
人生の傷といえば言って良い
痛いのは痛いでしかたない
だけど、早く優しく癒してくれる漢方薬を見つけよう
自分に遇った処方箋
福島の明日
経済の明日は自然現象で来る
必ず来る、神戸のように
置いてかれないように君の人生の明日も来さそうよ
埋れないように
邪魔な頭の人はほっといてください
窓を開ける 水崎野里子
あなたの
やさしい声が聞きたくて
開ける こころの窓
不思議な声
小さく灯す
小さなしあわせ
私は羽ばたく
小鳥
風 水崎野里子
風が吹く
風に向かって歩こう
息が出来なくなっても
きっといつか
おひさまの風が来る
スカートを翻す
春のダンス
パリの空の下 ―― Sous le Ciel de Paris 水崎野里子
街の灯火の中に
投げ出された 幾多の銃弾
命は花火 炸裂する
憎しみはいつもゲルニカの絵を描く
遠い日の エディット・ピアフの唄
今 響き渡る
〝太陽が空から落ちて来ても
海が突然 干上がっても
あなたの愛があれば 本当の愛があれば
どんな事でも 私は平気〟
窓は火の玉を呑み込む
窓は叫ばない
破壊されたガラスが号泣する
幾千の行き場のない難民は
今日もさまよう 食糧と眠る場所を求めて
彼らに口を開ける 愛はどこだ
空はどこだ
窓はどこだ
*以上四行はピアフの「愛の讃歌」の原詞訳(直訳)。英訳を参照した。
越路吹雪などにより日本で歌われた日本語版「愛の讃歌」の歌詞は
岩谷時子の大胆な翻案訳である。岩谷時子は作詞家として名を馳せ
るが実は終始、越路吹雪の付き人として生きた。独身を通した。ち
なみに越路吹雪の夫は内藤法美。彼は旧制第一高等学校(=現在の
東京大学)卒の越路吹雪の年下の夫である。越路吹雪の歌の音楽担
当、ピアノ伴奏、リサイタル構成をしていた。
鴉(からす) 山本なおこ
いい色の火だ ゼラニウムの赤ににている
どんな木をくべたらこんな火の色になるのだ
ろう 雪が降っていた 季節はずれの雪が音
もなく火の上にも降った が 火はいい色で
燃えていた
火の主はいないらしかった 手をかざしてい
ると ぱあんと銃声がとどろいた 薄青い夕
闇を背に 男が 銃口を空に向けたまま立ち
あらわれた 男は私をとがめはしなかったが
あきらかにいらだっていた 歯を鳴らすたび
眼の下の痣(あざ)がぬくりと動いた 男は何の獲物
も下げていなかった
私はきびすを返すにもひどく手間どった ど
こかアシカを思わせる男の眼と 銃口が私を
縛っていた しゅっと雪片が銃口にすいこま
れた 男は口の端でふっとわらうと これで
ええんかい らんぼうに銃をほうった 私は
軽いめまいを感じながらぎくしゃくと歩いた
いったい獲物は何なのだろう 私がぼんやり
考えだした時 ギャオ ギャオ ギルル 竹
やぶの空が黒々と包みこまれた 鴉だ とた
んに私は思いだした 去年の夏 ぶどう園の
縁飾りのように 一列横隊で吊り下がってい
た 黒の革袋 おどし袋 臭い袋
それにしても 夏場まで 冷凍にしておくつ
もりだろうか ぱあんと銃声がとどろいた
ふり向くと 火の上あたりに 鴉が みせし
め袋のかたちで ゆっくりと落ちていくのが
見えた
父と子 中西 衛
(彼の合理的な論理は 耐えがたくカンに
障るものなのだ)
その一個の排他性が
分かり過ぎるほど
分かっているのだが
奔放な
しかも不安定な生い立ちに
小さなわだかまりが
激しくぶつかり
押し合い
ひしめきながら
増殖され
毀れ
そのたびに
かけらは飛び散り
引き返しようのない
影をひきずって―
自己の運命に気づくとき
いたわりようのない
苦しさに
いつまで耐えて行かねば
ならないのだろうか
〈シリーズ・手〉 暮れ方 原 和子
物たちが
みんな しずかに
古びていく 時刻
いろ褪せたカーテンに
くるまれる 西日
母の残していった
小引き出しを 撫でる
うずくまる猫を
撫でる
柱の傷を
撫でる
たとえようもなく
遠く
いとおしいものを
しきりに 呼びながら
わたしも
しずかに
古びていく
終ったもの 原 和子
終ったものは 寂か
心電計
死者の手
入日のあと
枯れた花
墓石
終ったものは
語りかける
息絶えた犬
終って
疼く
恋
牛島富美二
現実
揺られ揺すられて壁にしがみつく
棚を飛び出した小芥子が三つわたしを打つ
その時すでにこの世を離れた別れの合図
――春来るも地震(ない)振る振る振る鬩(せめ)ぎ合う…
伺い
唇は亡びていませんか
歯は音を立てていますか
丹田に力が入っていますか
――新年に言葉ひとつの願い事…
大雪
涙が固まると大粒の雪となって
ふだんは暖かい地方にもふいに訪れ
溶解して滲(し)みだす痕が泣きじゃくる
――みちのくの雪の重さも痛みをも…
恩寵 牛島富美二
こういう日差しを歩いていると
昔人の謡(うた)がよみがえり
恋風に吹かれながら
ふっとこぼれる涙に立ちどまる
もはや
過ぎ去りし日々の思い出ばかりに
責められて足もおぼつかない
そのうえおたまじゃくしや水蠆(やご)もなく
捧げた菫も薄荷も消え
歩いたはずの足跡も失せて
ほんとうに独りで歩いたのか疑ってみる
けれど
足の向く先はみんな通(かよ)った独りの道
その道の小石を転がしながら
その道の草を笛にして
やはり独りだけの音を奏でてみる
すると呼応するものが遠くから
呼びかけてくるこのひととき
刻(とき)も宙(そら)も留まらないけれど
みんな通った独りの道は
独りで通った道だから
足音の代わりに
草笛の謡が今日も流れる
春夏秋冬―2015 きだりえこ
若菜粥常世の春と思ふべし
蝋梅の花に宿れる弥勒かな
暮れなずむ泊に春は帆を降ろし
拘置所の窓より櫻見へますか
ゆりかごの夢のかたへに柚子の花
七十は女盛りや藤の花
産土の水引き入れて金魚かな
忘れめや八月六日の蝉時雨
襖絵の青き波濤へ今日の月
みちのくや花野に眠る髑髏
おもねるな誹るな愚痴るな霜の朝
ヨクイキヨ硫黄島より父の文
一本橋渡れ 斗沢テルオ
よりによってその年は大雪で
天間林村坪川支流
こんもりと雪を盛り上げた一本橋
母は
必死の形相で丸太を凝視め立ち竦んでいた
背の温もりには緊張の汗など伝わることもなく
寝入る生後六ヶ月の末妹
降りしきる雪はネンネコと角巻で
小さな かまくらをつくっていた
渡ねバ――
渡らねバ――
僅か三メートル足らずの一本橋
凍み大根(デゴ)作りにはちょうどいい流れ
けれど
懸命に渡り終えたその瞬間(とき)から
一本橋は戻り橋
行きも怖いが帰りも怖い
ようやく辿り着いた農家のカッチャは
このとおりの暮らしで製材加工費(フギチン)は払えネ
と囲炉裏の傍で首を垂れる
代わりに手にした少しばかりの菜
表は吹雪 涙さえ凍てつき頬を伝わず
泣いて困らせることのない背の子だけが
僅かに安堵の笑みをつくらせる
渡ねバ――今度は戻り橋
渡らねバ――家には帰れぬ
腹空かした子らと 酔い潰れた男の居る家に
俺の目の前の一本橋
師走の不況風に晒され立ち竦んでいる
従業員や家族の顔が浮んでは消える
母とは比べものにならぬどたんば
されど渡れずにいる不甲斐なし
降りしきる雪の中から声が聞こえる
渡(わだ)れ――一本橋渡れ!
母の声が背中を押す
ほら――勇気(ジグ)出して 渡れ!
陽のまだら 秋野光子
母が木洩れ日の中にいる
顔に秋日が射し
頭の方に影がゆれている
そんなに濃いかげりではなく
笑顔で 楽しそうに話し
張りのある元気な声で喋っている様子も
ずーっと何十年も
変わりない母である
話すテンポも早く
会話の切り替えや 回転が早い
けれど 時々
テレビを見ている顔は
どこかへ行っている顔をしている
電話で話している時
あれやら これやら リフレインする
私 知りません と云う
家の近くにはじめて出来た
回転ずし屋へ 私を誘った
海老のにぎりが好きで
目の前へ来たら大喜びで食べ
二つおいて又 海老が来た時
「イヤー珍しい 私は海老が大好き」と云う
「今食べたとこやんか」と云うと
「あほなこと云いナ 久しぶりや」と怒った
私は口を開けたまま 黙った
子宮ガンとは きれいに縁切りした四十代半ば
胆のうの切除をした七十三歳
心臓の冠動脈弁を三つ
人工弁に取り替えもした七十八歳の時
八十一歳の今 週二回教室へ通って
手編みのセーターを編みつづけ
息子や娘の家族全員 多くの知人に配っている
三味線のお稽古に 週一回京都から大阪へ
今 母は
曇り時々晴 又は晴時々曇りの
まだら陽の中に
背すじを伸ばして立っている